戦後知識人の肖像②(2023年12月25~29日)
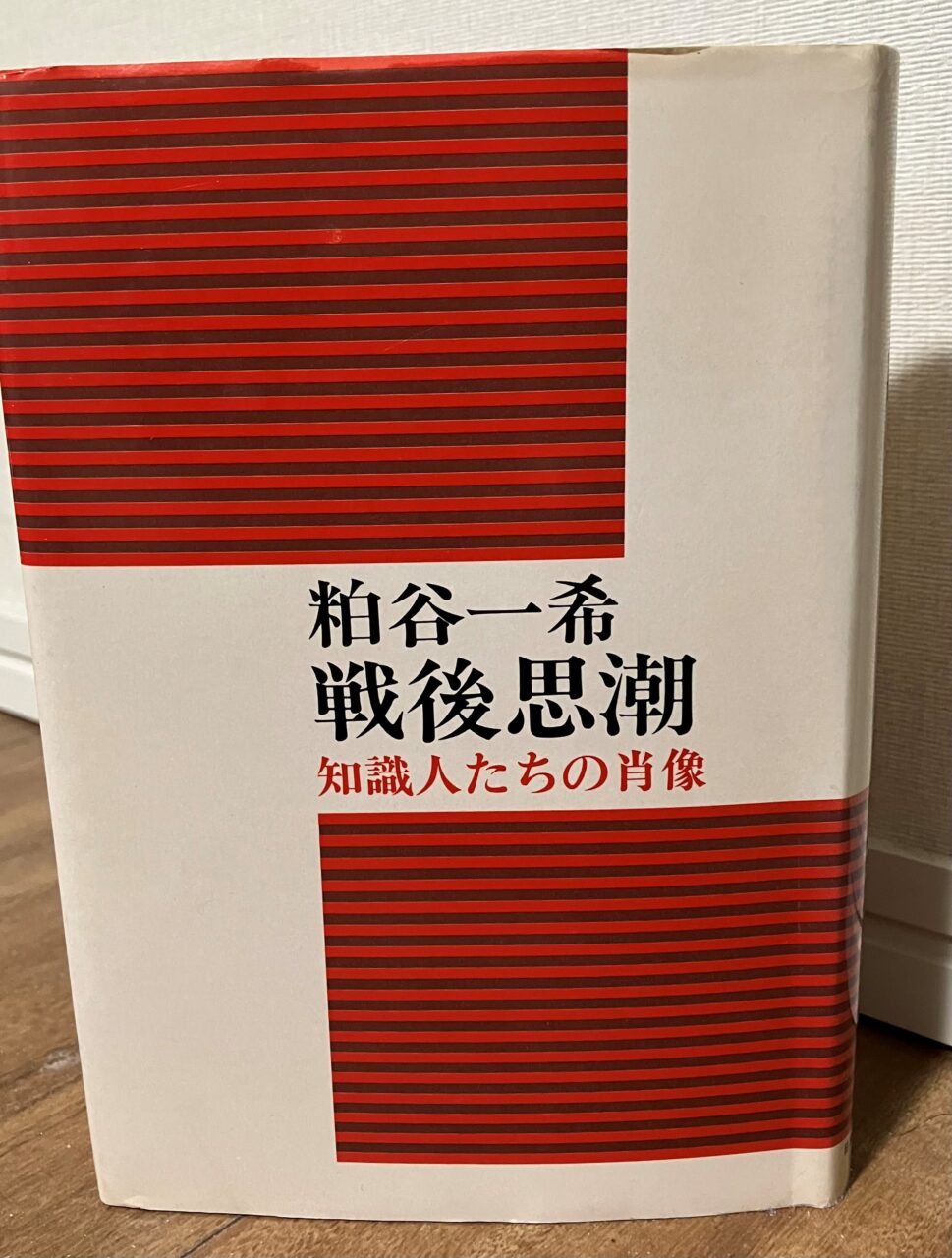
*** きょうの教養 (戦後知識人の肖像⑥)
⑥吉本隆明の独創性 いいだももが、都会秀才の軽妙と饒舌を伴いながら労働運動と農民運動の中に潜行してゆき、谷川雁が九州の炭鉱の中に腰を据えて逆説とアイロニーを駆使して政治的工作を自認した時、そこには詞を捨てた詩人のダンディズムとエリーティズムを嗅ぎ取れないわけではない。
しかし、吉本隆明(1924~2012)の場合、ダンディズムとエリーティズムに無縁であり、叙情詩人と武骨な徹底的戦闘性の不思議な結合が、その骨格を成している。熊本・天草出身という両親の資質や東京の下町育ち、私塾の優れた教師の感化、米沢高工、東京工大といった教育環境も性格形成に深く刻印しているであろうが、やはり戦時下の彼が正直な軍国主義青年であったという、敗戦の衝撃が最も大きく作用しているように思われる。
吉本の発想と文体の特徴は、強靭な思索性と体系性、虚飾を排して本音に迫る感受性、妥協を許さぬ戦闘性にある。時として誇大妄想に近い幻想を感じさせ、マナーを知らぬバーバリズムの響きをも思わせるものがあるが、彼が大学というアカデミズムとも、文壇という名の商業ジャーナリズムとも異なった生活基盤に拠点をおき、営々としてたゆまぬ学問への志と精進が、それを補って人々を圧倒する。偽善的秩序を本能的に嫌う青年学徒をひきつける秘密はそうした吉岡の生活スタイルと無縁ではあるまい。
原始キリスト教の原典批判を通して、「反逆の倫理」という副題をつけた一文で、「秩序にたいする反逆、それへの加担というものを、倫理に結びつけ得るのは、ただ関係の絶対性という視点を導入することによってのみ可能である」と書いている。人間関係・社会関係の優位という唯物論に立ちながら、原始キリスト教を、ニーチェとマルクスという反キリストの系譜で裁断した壮絶な文章だが、この独創的な出発点こそ、彼に戦後反体制運動の体制化を、「擬制の終焉」と裁断できた自由な自立の視点を可能にしたものであろう。
*** きょうの教養 (戦後知識人の肖像⑦)
◎司馬遼太郎がゆく 福田定一という戦後派の青年が、あるとき司馬遼太郎(1923~1996)という作家に変身して以降の足跡は、一種奇跡に近い不可思議なものがある。おそらく司馬が、歴史的人物を自家薬籠中のものとし、掌中の人物を語るがごとく蘇らせる手法を身につけたのは、子母沢寛の「新撰組始末記」を下敷きとして書いた「新選組血風録」のあたりからではないかと思われる。忠臣蔵と並んで新選組は日本の庶民の中に生き続ける人間集団といってよい。メンバーひとりひとりに、作者の解釈を通して、眼前にある人物群像のような生命を吹き込んだとき、作者は自由自在に歴史との対話を可能とする手法を身につけたのであろう。
「龍馬がゆく」「燃えよ剣」「国盗り物語」と短時日の間に展開された歴史文学の世界は、一瀉千里の趣きがある。特に「竜馬がゆく」と「坂の上の雲」は、坂本龍馬という、もっとも司馬好みの自由人をとらえることにより、明治維新という大変革期を描き、また、秋山好古・秋山真之という兄弟をとらえることで、日露戦争を描き切るという大事業を成し遂げた。
戦後日本人にとって、この二大長編の持つ意味はきわめて大きい。敗戦による日本人の自己否定は、明治以降の歴史のすべてに及び、屍に近い状態で放置されていたといえるだろう。歴史学者たちは明治維新の解釈に終われ、天皇制国家の非民主性を論難することに血道をあげていた。けれども当時の人が自らの血と汗で築いた明治国家は、反面に暗い部分を有していたにせよ、明治の青春であった。記憶の底に沈む映像を彷彿と甦らせた功績は大きい。
その時、司馬文学はひとつの国民文学になったのであり、司馬は国民的歴史家になった。知識人、政治家、経営者から町の庶民に至るまでが熱中した。文体は簡潔、平明でダイナミックであり、語り口はさわやかに能弁である。戦後解放された日本人は、司馬文学の中に初めて最も共感できる近代的な感受性の表現者を見出したといえるだろう。
*** きょうの教養 (戦後知識人の肖像⑧)
◎大江健三郎の冒険 大江健三郎(1935~2023)は、石原慎太郎や開高健と同時期に芥川賞を受賞したが、当時、東大仏文科の学生で23歳の若さだった。石原、開高、大江の世界には新しいエネルギーの奔流が感じられ、それ以前の「第三の新人」が、占領下日本の「無力感」の表現であったとすれば、新世代は高度成長への予感を表現していたといえる。石原、大江は、同世代の評論家江藤淳、演出家浅利慶太などとともに「若い日本の会」を組織するが、1960年安保を前に戦後民主主義の論理と活力が最も高揚した季節でもあった。
江藤がサルトルの影響下にあったように、大江の文学的出発もサルトルの文体・発想の深い影響の下に始まっている。サルトルの「アンガージュ」が当時の知識人への強いアピールを持っていたとすれば、そこには新しい未来が約束されているはずであった。けれども60年安保の挫折は、若き人々の歩みを大きく隔てていった。気質的にスポーツマンであった石原にとって、文学も映画も政治もそれほど異質な世界とは思われなかったであろう。俊敏な都会秀才であり、秩序感覚が基礎にある江藤が、文明批評家として伝統に回帰していったことも極めて正統的であった。
大江が最初の出発に固執し、戦後民主主義の論理と前衛的感受性の冒険を維持していることは、「持続する志」であろう。そこに大江固有の困難な道行きがある。大江の文学的感受性が豊富であればあるほど、発想と文体の創造的破壊ともいうべき冒険を試みなければならなかったが、底にある論理としての戦後民主主義が、守旧化し風化していくことが、常に背後からその実験精神を脅かすことになる。
けれども幼少時代から自閉的であり、想像力により架空の世界に遊んだ大江が、自らの資質を文学に昇華した時、それは確固とした根を持っていたことを、長い創作活動は証明している。「死者の奢り」に見られる「監禁状態」と徒労感、死体処理場での管理人とアルバイト学生と妊娠している女子学生という暗い舞台での奇妙に明るい感受性、生と死のコントラスト・・・。それらは大江の文学的強靭さが出発以来のものであることを教える。
*** きょうの教養 (戦後知識人の肖像⑨)
◎松下圭一の先見性 戦後世代の政治学徒の中で、松下圭一(1929~2015)は、最もジャーナリスティックな政治感覚と柔軟な先見性を発揮しながら、政策レベルで革新勢力に影響力を与え続けてきたひとりである。松下の役割は、1960年安保以後、革新陣営が挫折感の中で低迷していた時、冷めた認識のもとに次々と革新勢力のための政策提言を打ち出したところにあった。「忘れられた抵抗権」(「中央公論」1958年11月号)を指摘した松下は、市民的自由のための実証科学、政策科学を高唱し、地域民主主義、都市政策の重要性をもっと早く捉えたのである。
保守勢力が60年安保以後、池田内閣の成立によって柔軟な対応姿勢を示し、革新勢力の中に構造改革派グループが台頭していった機運と照応していた。保守勢力が安定多数派を形成していった季節に、中央突破という性急な政治主義を抑え、都市や地方自治体という身近な日常性から政治生活や政策的方向を再構築していくことであった。
こうした発想は当時の革新勢力に一定の方向性を与え、中央政治の動向とは別に、大阪、京都、東京、横浜と次々に革新自治体を成立させていった。けれども革新自治体のその後の成り行きが暗示しているように、市民共和と福祉社会もまた大きく変貌している。人権と市民的権利、労働基本権と労働組合といった近代社会の基本的観念自体が、今日の状況の中で新しい検証を要請されているように思われる。それは保守・革新を超えて、より柔軟な対話の中で、模索されるべき政策次元を超えた文明の主題ではあるまいか。
*** きょうの教養 (戦後知識人の肖像⑩)
◎伊東光晴の柔軟性 松下圭一が市民的自由の政治学を展開することで革新勢力の基本戦略と政策を方向づけたとすれば、経済学の領域で同様の役割を果たした者は、伊東光晴(1927~)であろう。一橋大学で杉本栄一の下で学び、都留重人のもとに就く。2人の師の影響が、伊東の発想の基本を養ったといえる。杉本は学問への情熱的姿勢、透徹した論理と強靭な思索力で他の追随を許さなかった。都留は、戦後の復興期に柔軟な現実感覚とアメリカ経験を生かして、経済安定本部で最初の経済白書を執筆した。行政能力と政策能力を兼備した学者であった。
伊東が早くから革新的信条を持ちながら、ケインズを著し複眼的視野の所有者であることを証明したことは、杉本の発想を継いでいるといえる。ジャーナリスティックな感覚と広い問題関心の中で、市民的経済学を展開していったことは、都留の発想・行動様式を継いだものと考えられる。池田内閣登場以降、日本の高度成長が顕在化することで、革新陣営は社会主義理論を振りかざすだけで対応できず、具体的な政策次元の論争でこたえなければならなくなった。国際関係の次元で、安保体制の是非を問い、非武装中立路線を主張する革新陣営の主題よりも、より日常的な具体性を持つ必要があったし、そうした能力を革新陣営は発揮できた。
日本の革新陣営の経済学は、1960年代に政策次元での有効性を近代経済学と競う状況にまできた。伊東、宮崎義一、宮本憲一、正村公宏といった人々の日本経済分析の業績は評価されてよい。伊東の「保守と革新の日本的構造」(1970年)は、そうした工程の里程標であろう。それにもかかわらず共産党・社会党・労働組合の守旧化ははなはだしい。マルクスとケインズから発想された経済学は、改めてマルクス→シュンペーターの路線から創造的革新を構想するべきではないのか。
