類語ニュアンス辞典(2024年2月5~9日)
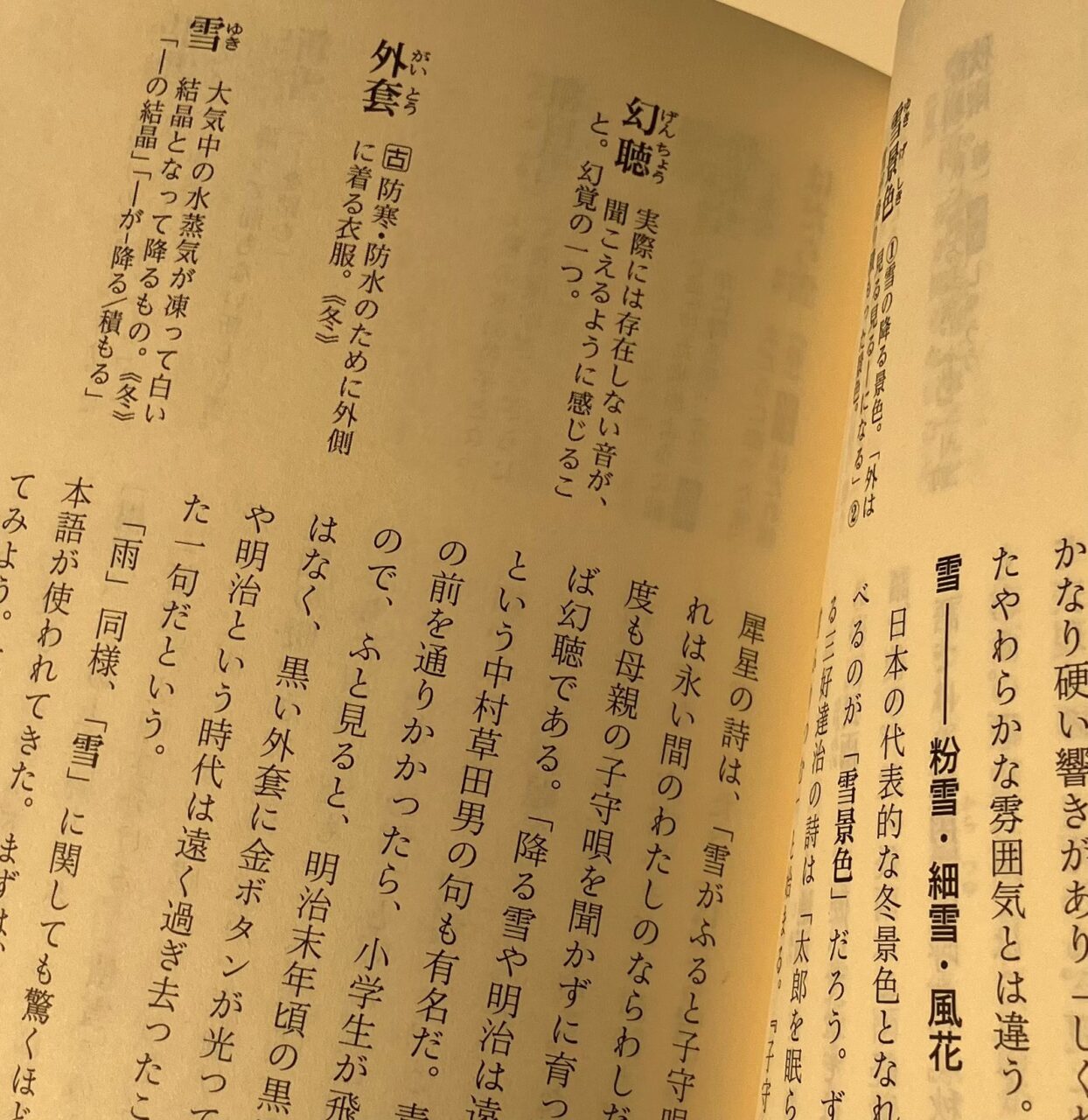
*** きょうの教養 (類語ニュアンス辞典①)
今週は「類語ニュアンス辞典」(中村明編著、三省堂)から、5つの言葉を選んで紹介する。日本語の豊かさについて、文学作品を交えながら解説する辞典だ。私の近著「本気の文章上達法を教えます」(セルバ出版)の178~179ページでも取り上げた。自分の名刺の肩書を考える時、迷った結果、「文筆家」にした。この辞典で「作家」の類語を調べ、「文筆家」の意味を確認した逸話だ。初回は「雪」。新沼謙治の「津軽恋女」では、「津軽には七つの雪が降る」(こな雪、つぶ雪、わた雪、ざらめ雪、みず雪、かた雪、春待つ氷雪)と歌われている。
◎【雪】 日本の代表的な冬景色となれば、「雪景色」だろう。「雪」と題する三好達治の詩は「太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ」と始まる。雪には驚くほど多様な日本語が使われてきた。気温の低い時に降る乾いた感じの雪を「粉雪」、気温が高めの時に降る大きく膨らんだ雪は形の似た花に例えて「牡丹雪」(ぼたんゆき)、湿ってべとつく感じの雪を「べと雪」と呼びならわしている。泡のようにすぐ溶けてしまう雪が「泡雪」(あわゆき)。同音の「淡雪」は春先にうっすらと積もる雪を指し、春の季語となっている。「小諸なる古城のほとり」で始まる島崎藤村の詩で千曲川の旅情を詠んだ一節に「しろがねの衾(ふすま=布団)の岡辺、日に溶けて淡雪流る」とあるが、早春の感覚的な発見である。
降り積もった雪が春まで残るのが「根雪」、その上にふり被さったばかりの軽い雪を「新雪」と呼び分ける。細かに降る雪が「細雪」で、谷崎潤一郎の長編小説の題名ともなった。ごく細かな場合は、「粉米雪」(こごめゆき)と呼ぶこともある。
降る量に注目すると、大量に積もると「大雪」と呼び、一度に大量に降り積もると「どか雪」という。降り方に関係なく、大量に雪が降ると「豪雪」という漢語で呼び、「豪雪地帯」などと使う。反対に少しだけ降るのが「小雪」で、小雪が「ちらつく」とか「舞う」と使われる。中原中也の詩に「汚れちまった悲しみに/今日も小雪の降りかかる」とある。空が晴れているのに風が吹き始め、桜の花びらが散りかかるように見えるところから「風花」と呼ぶこともある。その冬になってまたは新年になって初めて降る雪が「初雪」で、物珍しい感じが漂う。小林一茶に「闇の世の初雪らしきぼんのくぼ」という句がある。うなじの真ん中の首にひんやりとしたものを感じ、触覚で雪をみるのである。
*** きょうの教養 (類語ニュアンス辞典②)
◎【風】 日本人は風の音や感触に季節感や様々な情緒を味わってきた。まず思い出すのは「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる」という藤原敏行の一首だろう。良寛は「風は清し月はさやけしいざ共に踊り明かさむ老の名残に」と詠んでいる。風が肌に爽やかに吹きわたり、月は澄み切って明るい。
「軟風」(なんぷう)は風力3の旧称(以下同じ)で、旗がはたはたとはためく程度の風を意味する。強く吹く激しい風は一般に和語の「大風」(おおかぜ)で総称し、漢語で「烈風」と呼ぶこともある。気象学ではいくつかの段階に分ける。まず急に激しく吹く「疾風」(しっぷう)は風力5で、池や沼に波頭が立つ程度の風を指す。和語の「はやて」がこれにあたる。強い風と認識されている「強風」は風力7で、風に向かって歩きにくい程度の風を指す。さらに強くなると風力11の「暴風」があり、風速毎秒30m前後に相当する。風力12の最も強い段階が颶風(ぐふう)だが、今では古めかしい響きがあるようだ。
渦巻くように吹く強い風を「旋風」(せんぷう)と呼び、和語で「つむじ風」と読む。風速30m以上になると「竜巻」と呼ばれる。人間の進行方向に向かって背中を押すように吹く風を「追い風」、逆に吹く風を「向かい風」と呼び、漢語ではそれぞれ「順風」「逆風」という。吹く時間帯によって、「朝風」「夕風」「夜風」と呼び分ける。なぜか「昼風」は意識されないらしい。風が止んで海が穏やかになるのが「凪」(なぎ)で、時間帯によって「朝凪」「夕凪」と呼び分ける。元日に吹く風が「初風」、止めば「初凪」と特別に読んで新年の気分を味わう。
立春が過ぎた頃に吹く強い南風が「春一番」で、春先に吹く強い南風を「春荒れ」「春嵐」、桜の花が満開のころに吹く強い風を「花嵐」、春に吹く暖かい穏やかな風を広く「春風」(しゅんぷう、はるかぜ)と呼ぶ。春に「風光る」と視覚的にとらえた日本人は、夏には「風薫る」と嗅覚的にとらえ、初夏に若葉の香りを漂わせて吹く風を「薫風」(くんぷう)と名付ける。強い場合は「あおあらし」と呼び、改まった場合には漢語で「青嵐」(せいらん)ということもある。青葉を吹き渡る爽やかな初夏の風を「緑風」(りょくふう)と呼ぶ。
*** きょうの教養 (類語ニュアンス辞典③)
◎【妻】 妻という言葉は、夫から配偶者を指す最も一般的な基本的和語である。「女房」という古風な和語も同じ意味で用いられた。「家内のやつ」とよく使われた「家内」は、へりくだって自分の妻をさしたが、今ではやや古風な感じになりつつある。島崎藤村の小説「破戒」にも「家内はまた家内で心配して」という例が出てくるが、字面からいかにも家庭の中に閉じこもっているような連想があるところから、近年は女性に敬遠される傾向がある。
「細君に頭が上がらない」と使う「細君」(さいくん)という語は、他人に向かって自分の妻をへりくだって言う言葉だが、かなり古風な感じを与える。「細」は肥満の度合いとは無関係で、取るに足りない存在の意の謙称である。「妻」を「サイ」と音読みし、「サイが申しております」と自分の妻を他人に対して少し改まって言う例も昔はあったが、現在ではほとんど見聞きしなくなったようだ。「かみさん」という言葉は、元商人や職人の妻を指した語で、永井荷風の「ふらんす物語」にも「巴里で宿屋のかみさんがくれた」という例が見える。自分の妻を、親しみと照れをもっていう俗っぽい表現としてよく使われた。適用範囲を広げて、「うちのやつ」「うちの者」とぼかす言い方にも発言者の照れが感じられる。
小津映画の「一人息子」に、大久保先生が自分の妻を「愚妻です」と紹介する場面が出てくる。夫からバカ呼ばわりされたくない世の奥様達の不評を買い、今では使うのに相当の勇気を要する。「荊妻」(けいさい)という言葉も自分の妻をさす謙称となっている。「荊」は「いばら」という意味で、中国の故事から出たという。「嫁」という和語は、息子の妻をさすのが普通だが、関西方面の出身者の中には、自分の「妻」をさす用法もあるように身受けられる。
「かかあ天下」と使う「かかあ」という言い方もある。時により親しみ・軽蔑・謙遜などさまざまな気持ちを込めて、自分の妻を呼ぶ古風な俗語である。「ワイフが里帰りしている」と重要な日本語を意味するためにわざわざ英語を借りて「ワイフ」と呼んだ時代もある。一見崇拝しているように見える「山の神」という言葉もある。実は尊敬しているように見せかけ、口うるさい女房を亭主がからかい半分に親しんでいう俗語である。
*** きょうの教養 (類語ニュアンス辞典④)
◎【健康】「健康」という漢語は、心身ともに元気な意味で広く現れる。「健勝」という漢語は主に手紙文の中で挨拶として用いられる。「健全」という漢語は、「健全な考え方」や「健全財政」のように抽象的な意味の拡大用法として盛んに使われる。「健やか」(すこやか)という形容動詞も心身ともに健康な状態を表す。日常会話より文章に用いられ、感触が柔らかく、詩的な雰囲気が漂う。
小津安二郎の映画「秋日和」に「お前また元気が出てきたな」というセリフが出てくるが、「元気」というのは体調がよく活力に満ちている状態をさす。日常の基本的な漢語で、健康状態よりも精神的な活力に中心があるように思われる。「丈夫」という漢語は意味が広く、「丈夫な生地」のように物品が頑丈な場合にも使われる。人間に用いた場合、健康で体がしっかりしている状態を指すが、いくらか古風な響きがあるかもしれない。「ピンピン」という語は元気以上に元気そうだが、文体的に属っぽいレベルにある。
「壮健」という漢語は、もっぱら体が元気で丈夫な意味を表し、改まった手紙や文章に用いられ、精神的な意味合いではあまり使われない。「無病息災」などと使われる「息災」という言葉も、無事で健康だという意味合いの古めかしい漢語で、古井由吉の小説の題材ともなった。恙虫(つつがむし)の害に合わない意味から出たらしい「つつがない」というやや古風な漢語は、病気や事故など格別の異常がないという場合に用いられ、健康状態だけではない。
「矍鑠」(かくしゃく)という漢語は、年齢の割に元気に活動している状態を指し、改まった会話や文章に用いられる。「達者」も体が丈夫だという意味で使われる。夏目漱石の「坊っちゃん」に「読み書きが達者でない」という例があるように健康とは無関係に優れているという意味合いでも使われる。「体調」という漢語は体の調子という意味で、「調子」は広く物事の進み具合や機械などの動きの滑らかさについて用いる。塩と梅酢による味加減を意味した「塩梅」は古風な漢語だが、健康状態について「どうも体の塩梅がよろしくない」と言うこともある。戦後は「按配」とも書く。
*** きょうの教養 (類語ニュアンス辞典⑤)
◎【粋】 織田作之助の「夫婦善哉」に「白い料理着に高下駄という粋な恰好(かっこう)」という例が出てくる。人の容姿、身なり、態度、身のこなし、あるいは建物、街並みなどが、さっぱりしていて洗練され、すっきりとした中にも、人の情に訴える品のいい色気が感じられる様子をさす。人情の機微に通じ、さばけているという意味にもなり、その逆の垢抜けないのは「野暮」である。
粋は漢語の「意気」から転じた和語らしい。「粋(すい)なお方やおまへんか」という上方の「すい」に対抗して、江戸の心意気を誇るため、同じ漢字を「意気」に通わせて使ったものだというのである。そこから出た「粋筋」という語は、それとなく男女の情事を意味する用法もある。「小粋」といえば、「ちょっと粋な」という意味合いになるが、粋な程度が小さいというより、どことなくあか抜けしていて、どの点か特定しがたい場合に使う傾向がありそうだ。
威勢が良く、強きを挫き弱きを助けそうな侠気が見え、身のこなしが洗練されている。そんな粋な男の様子を「いなせ」と呼ぶ。江戸日本橋の魚河岸の若者が鯔(ボラ)の幼魚であるイナの背に似たまげを結ったところから出たともいい、漢字で「鯔背」(いなせ)と書くこともある。「乙」という語もちょっとしゃれていて気が利いている様子をさし、「味」という語も、物事の味わい、趣について用いる。
「枯淡」(こたん)という語も、俗を離れ、あっさりしている中にも趣があり、深い味わいが感じられる様子をさす。「洒脱」という古風な漢語も、飾りや気取りがなく俗を離れた趣をさす。「洒落た」という表現は、気が利いて、洗練され、垢抜けた様子を意味する。近年「こじゃれた」という俗っぽい言葉をしばしば耳にする。「粋」から「小粋」が出たように「洒落た」に「小」をつけてちょっと洒落た感じの意味を表そうとしたように思われる。
これら類語の底あるのは、「垢抜けた」感じ、「洗練された」趣だろう。「垢抜ける」は、容姿や態度や身のこなしや行為や技芸などがスマートで都会風であり、泥臭さや素人らしさが感じられない域に達することを意味する。一方の「洗練」は、動作や趣味や技芸や作品などを、高尚で優雅な感じになるまで磨き上げることをさす。似たような意味だが、「洗練」が磨き上げて身につけた感じが強いのに対し、「垢抜けた」は持って生まれたセンスの場合もありそうな雰囲気がある。
