河合隼雄の「働きざかりの心理学」(2024年12月2~6日)
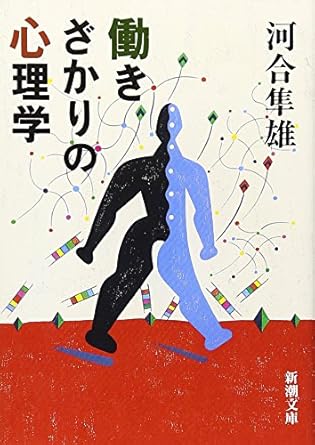
*** 今週の教養 (河合隼雄の働きざかりの心理学①)
今週は心理学者の河合隼雄(1928~2007)の著書「働きざかりの心理学」(新潮文庫)から紹介する。刊行は1981年。高度成長が終わり、石油ショックに揺れる時代で、バブル景気の始まる前だ。終身雇用の時代だが、今と比べた共通点と相違点を考えながら読むと、味わい深い。
◎疲れる「働きざかり」 30歳過ぎの会社員が相談に来た。会議中に急に動悸が高まってきて、「死ぬかもしれない」と思うほどの状態になった。様子の激変に同僚も驚いて、救急車を呼んでくれた。ところが医者の診断では、別に異常なところはない。元気になり、その後は何事もなく仕事を続けた。ところがしばらくして同様の発作が起こり、以前と違う医者に行くと、あっさり「心臓神経症」と言われたという。
この人と話しあってみると、会社の経営方針についての批判をとうとうと述べる。批判というより非難、不満に近い。会社の批判は世の中全般へと拡大され、世の中の人たちは利益ばかりを追求して大切なことを忘れている、自分のためばかりを考え、他人を蹴落とすことなど何とも思っていない、などなど。勢いのいい話し方に接していて、私はふと大学1、2年生の姿を思い浮かべた。我こそは正義の味方であり、世の中はすべてダメだという勇ましい姿も、大学生あたりだと様になるが、30歳の人ではあまりピッタリこない。
自分の人生に意見や責任を持つとき、人間はそれほど簡単に正義の旗ばっかりは降っておられないものだ。働き盛りの人は何らかの意味で責任を負わされる。会社においても家庭においてもそうである。責任を持つということは、光と影との両面を背負うことである。影の方ばかりを見て、世の中こんなものであると割り切るのも馬鹿げているが、矛盾を背負うことによって疲れてくる人もある。あちらが痛い、こちらがだるいと訴える働き盛りの人は、案外多いものである。これらの人は働き盛り、つまり大人になる関門を越えられず、青年期の間に成し遂げておくべき課題を引きずったままにしているので、疲れてくるのである。そのような人は、過去を振り返って自分の弱点を補強し、大人の世界に参入する努力をしなければならない。
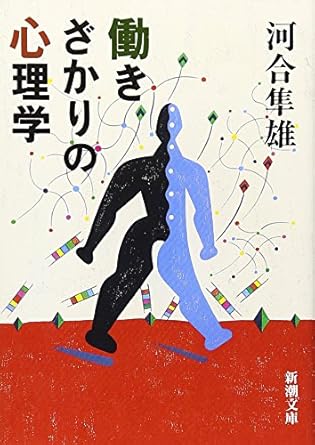
*** 今週の教養 (河合隼雄の働きざかりの心理学②)
◎虫が好かぬ関係 職場の中に「虫が好かぬ」人間がいて、不愉快なことがある。初めて顔を合わせた時、なんとなく虫の好かぬ奴だなあと思ったが、まさにその通り。表面的には普通に付き合っているのだが、その人のすることなすこと、腹に据えかねる感じがして、イライラしてくる。誰しも経験されるであろう。
日本語の「虫が好かぬ」という表現は、なかなか味のある言葉で、私とかあなたとかではなく、虫を主語にしているところが面白い。嫌いは嫌いだが、自分にとってはもう一つ訳がわからないという感じがうまく出ている。訳のわからないままにしておくのではなく、もう一歩踏み込んで考えた人は、虫の好かない相手のすることは何でも嫌になる。そんな時は、イライラするのはどんな時だろうかと思い巡らしてみることである。
30代の働き盛りの会社員Aさんは、虫の好かぬ同僚についてあれこれ思い巡らしているうち、その同僚が部長と話し合っている態度が一番気に入らないらない事に思い至った。「なんだあのへつらった態度は」と思った途端、Aさんは笑い出してしまった。あれは俺の姿そのものではないかと思ったからである。と言ってもAさんは、上司にへつらう人というのではない。そんなことをするものかと拒否しつつ、やはりへつらう気持ちも心の底には結構存在しているものだなと気づいたわけである。
Aさんはこのことに気づいてから、その同僚を見ると、それほど嫌でもないし、以前に感じたほど別に上司にへつらうような人物にも見えなかった。結局、虫の好かない関係は解消されたが、一緒に飲んだ時、実は最初の頃は嫌な奴だと思っていたのだが、と告白すると、相手もAさんに対して、実は僕もそう思っていたのだと言って、大笑いになったのであった。虫の好かない相手は、自分があまり気づいていない影の部分を拡大して写してくれる鏡のようなものである。だから相手をよくよく観察し、少し余裕を持った気持ちで見ていると、自分のことにハッと気づくことがある。
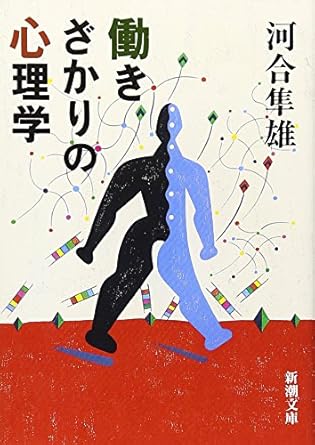
*** 今週の教養 (河合隼雄の働きざかりの心理学③)
◎つき合いの難しさ 夜遅く帰ってきた夫が妻に言い訳がましく「どうも付き合いでね」ということは多いのではないか。妻は心の中で「好きなことをしてきたくせに、ごまかそうとしている」と思うこともあろう。しかし同僚たちに「つき合いの悪い奴」と目されると、人間関係が上手くいかず、仕事に支障をきたしてくることもある。職場の人間関係は機能と心情的な結びつきによっているが、バランスがなかなか難しい。欧米の会社と比較すると、日本における心情的な比重は相当大であると考えられる。
Aさんはつき合いを大切にする人である。同僚が飲みに行こうと言うと、必ず一緒に行く。上司が休日ゴルフに誘うと、喜んでやってくる。ところがつき合いで少しずつ無理が生じてくる。飲んで喋っているうちに、その場にいない人の悪口を言いだし、言わずもがなまで言ってしまう。帰宅して悪口を言いすぎたと思って電話で訂正してみたり、それとなく悪口を言った当人のご機嫌を伺ったりしなくてはならない。人間はあちらにもこちらにもつき合いよくはできないのである。つき合いにエネルギーを取られすぎて、肝心の仕事が疎かになってくることもある。そうなると職場での評判も悪くなりがちで、ますます付き合いに精を出さねばならない。こんな悪循環を繰り返している。
Aさんはある日、大変ショックを受けることがあった。夜遅く帰ってきたAさんに中学生の息子が「お父さんはいいね、毎日飲んだり麻雀したりで」と言ったのである。妻もまったく賛成という顔でいる。Aさんはつき合いをしても会社であまりうまくいっていない。家でまで嫌味を言われ、全く立つ瀬がない。Aさんはよくよく考えているうちに、つき合いに精力を費やしている最大の理由は、自分の自信のなさにあると気づいた。ほうっておかれるのが怖いのである。Aさんは仕事で他人に負けないようになろうと決心した。自分の仕事に自信をもってくると、不思議なことにつき合うべき時と必要のない時がよく見えてくる。いろんなつき合いが、自分を活かすのか、殺すのかを再点検してみるのもいいではないだろうか。つき合いに個性を埋没してしまうのは残念なことである。
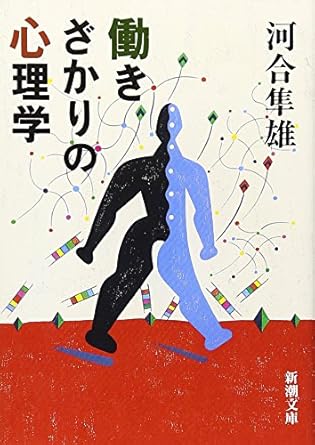
*** 今週の教養 (河合隼雄の働きざかりの心理学④)
◎劣等感とのつきあい方 劣等感はどうも始末におえない。何かの加減ですごく腹が立って、馬鹿げた怒り方をしたものだと思ったりする時、よく考えてみると、自分の劣等感が関わっていることに気づく。同僚と雑談している時、ある人は英会話がよくできる、たいしたものだという話題になると、急にムキになって「英会話が出来たからと言って大した人間とは決まってないよ」と言い、場をしらけさせてしまう。こんな時、英会話に劣等感を持っていることが多い。いや自分はそんなことはない、英会話のできる人を尊敬しているという人もあろう。しかし、尊敬する度合いが過ぎていることが多いようである。劣等感の存在は、人間の平静心を失わせるので、判断が狂ってしまうのである。
劣等感の原因には2種類ある。努力によって克服できるものと、できないものがある。英会話なら努力すれば克服されてくる。しかし、背の低いことや自分の職業に劣等感を持つ人などは、努力によって変更することができない。背の低いAさんは「自分は背が低いが、人間が小さいと言われないようにしよう」と思った。背の低い大人物は存在する。他の人ならせこせこするような時でも、努力を積み重ねた。そのうちに周囲の人もAさんを認め出し、大きい人間として扱うようになってきた。劣等感の原因でくよくよするより、そこから派生する自分のできることを探し出し、努力を続けることが、遅いようで早い劣等感克服の道になるように思われる。
深い劣等感はなくならないものかもしれない。しかし、よく考えながら付き合っていると、新しい努力を始める起爆力となったり、思いがけない自分の欠点に気づかせてくれたりする。それは普段は何かと困らせることが多いが、いざという時に思いがけない良い忠告を与えてくれる不思議な友人のようなものである。実際我々は、付き合いがたい劣等感という友人とのつき合いを通じて、人を愛することを学んでいくようである。
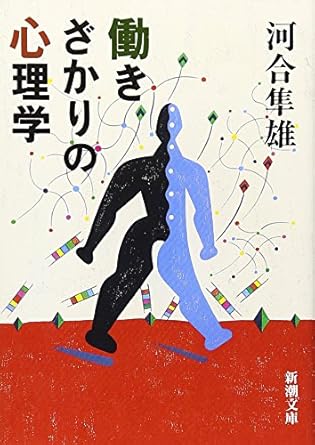
*** 今週の教養 (河合隼雄の働きざかりの心理学⑤)
◎陽の当たらない場所 Bさんは仕事熱心な人である。有能で入社以来、常に表街道にいた。同僚より早く課長になり、張りきっていた時、結核になってしまった。「今時、あなたのような年齢で結核になる人は珍しいですね」と医者に言われ、休職になった。思いがけない病気で急に陽の当たらない場所にゆかねばならなくなった。人間誰しもそのようなことを一生のうちに何度か体験するのではなかろうか。我が国では、個人の能力や個性より、全体のバランスを考慮する。能力から考えると本部の課長になるのが適切でも、年齢とか他との釣り合いを考慮して、支店勤務に回されることもある。このような時、その人がいかに生きるかによって、その人の人生行路が決定的に決まることがある。
我々心理療法家は、人生の分岐点でつまずき、さらに落ちてしまったような人に会うときがある。酒に溺れてアルコール中毒になったり、競輪や競馬で借金を作ったり、転落の道はいくらでもある。きっかけは気の毒な事情もよくある。部下の使い込みの責任をとって左遷されたとか、昇進の道をあくどい中傷で絶たれてしまったとか。同情すべき、全くの不運としか言いようがないこともある。しかし考えてみると、人生行路が陽の当たるところばかりということもありそうにない。誰しも不運に泣く時はあるが、それをどう受け止めるかという点に差が生じてくる。
Bさんは病気の宣告を受けて悲観したが、不思議なことに、心の片隅で何だかホッとしているような感じがあった。帰宅して病気のことを妻に告げたが、妻も同じように感じたという。主治医に話してみると、「そういう人は案外多いんですよ」という返事が返ってきた。医者は「一度ゆっくり休めということですな」と付け加えた。復職後のBさんは焦らなかった。陽の当たらない場所であったが、そこから見る世界は、陽の当たる世界とは異なる趣があった。人の親切も前よりよくわかるようになった。周りは「Bさんは病気をして人間が一回り大きくなった」と評した。こうなってくると、また陽の当たる場所へと呼び戻されることになろう。そうなっても彼は、陽の当たる場所にいる者だけが人であるような、馬鹿げた態度で人に接するようなことはないだろう。

