西洋哲学の名著(2025年4月28日~5月2日)
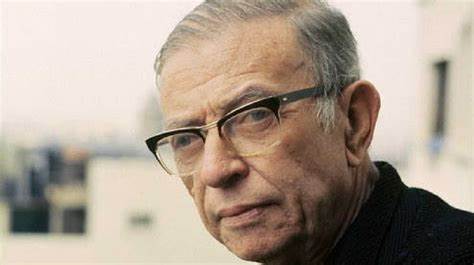
*** 今週の教養 (西洋哲学の名著①)
今週は西洋哲学の名著を紹介する。人名や書名は知っているが、読んだことがない人も多いだろう。デカルト、カント、ヘーゲル、ニーチェ、サルトルの著書を紹介する。いずれも難解だが、雰囲気の一端を味わうのも悪くない。
◎「方法序説」デカルト(1596-1650)。「近代精神確立の書」とされる。有名な「我思う、ゆえに我あり」の一節がある第4部から紹介する(岩波文庫)。
私は、それまで自分の精神の中に入っていたすべては、夢の幻想と同じように真でないと仮定しよう、と決めた。しかしそのすぐ後で、次のことに気がついた。すなわち、このようにすべてを偽と考えようとする間も、そう考えているこの私は必然的に何者かでなければならない、と。そして「私は考える、ゆえに私は存在する」(我思う、ゆえに我あり)というこの真理は、懐疑論者たちのどんな途方もない想定といえども揺るがし得ないほど堅固で確実なのを認め、この真理を、求めていた哲学の第一原理として、ためらうことなく受け入れられる、と判断した。
それから、私とは何かを注意深く検討し、次のことを認めた。どんな身体もなく、どんな世界も、自分のいるどんな場所もないとは仮想できるが、だからといって、自分は存在しないとは仮想できない。反対に、自分が他のものの真理性を疑うおうと考えること自体から、極めて明証的に極めて確実に、私が存在することが帰結する。逆に、ただ私が考えることをやめるだけで、仮にかつて想像したすべての他のものが真であったとしても、私が存在したと信じるいかなる理由もなくなる。
これらのことから私は、次のことを知った。私は一つの実体であり、その本質ないし本性は考えるということだけにあって、存在するためにどんな場所も要せず、いかなる物質的なものにも依存しない、と。したがって、この私、すなわち私をいま存在するものにしている魂は、身体(物体)から全く区別され、しかも身体(物体)より認識しやすく、たとえ身体(物体)がなかったとしても、完全に今あるままのものなのであることに変わりはない、と。
◆
*** 今週の教養 (西洋哲学の名著②)
◎「純粋理性批判」カント(1724~1804)。ドイツの哲学者で、理性に重きをおく啓蒙思想の完成者。序言と第一部から引用する(筑摩書房)。
【序言】Ⅰ純粋な認識と経験的認識の区別について 我々の認識はすべて経験とともに始まる。そのことには、みじんも疑う余地がない。というのは、認識能力が対象によって呼びさまされて働かないとすれば、他に何によって呼び覚まされるというのであろうか。対象は我々の感覚を刺激し、一方では自ら観念をもたらし、また一方では我々の知性活動を作動させる。その知性活動は、諸観念を比較し、結合し分離し、そのようにして完成的な印象の生の素材を対象の認識に仕上げるのである。そして、この対象の認識が経験と呼ばれるものである。それゆえ、時間的な順序で言えば、我々におけるどんな認識も経験に先立つものではなく、すべての認識が経験とともに始まるのである。
Ⅰ 超越論的原理論 第一部 超越論的感性論 どのような仕方で、またどのような手段によって認識が対象に関係するにせよ、認識が対象に直接関係するのは直観をとおしてであり、手段としてのあらゆる思想が向かう先も直観である。しかし、直観は対象が与えられる限りでのみ生じる。このことはしかし、さらに少なくともわれわれ人間にとっては、対象が我々の心的能力をある仕方で触発することによってのみ可能なことである。
われわれが対象に触発される仕方を通して観念を得る能力(受容性)、それを感性という。それゆえ感性を介して、われわれに対象が与えられるのであり、感性のみが我々に直観を供給するのである。一方、知性によって対象は考えられ、知性から概念が生じる。しかし、思考はすべて、じかに(直接的)にであれ、めぐりめぐって(間接的に)であれ、とどのつまりは直観に関係しなければならない。すなわち、われわれ人間にあっては、感性に関係しなければならない。というのは、それ以外には、われわれに対象は与えられようがないからである。
◆
*** 今週の教養 (西洋哲学の名著③)
◎「精神現象学」ヘーゲル(1770~1831)。ドイツ観念論の完成者と言われ、この著書は哲学史上きわめて難解とされる。感覚というもっとも身近な段階から数知れぬ弁証法的過程をへて、最高次の「絶対知」へ至る過程を考えた(ちくま学芸文庫)。
【序論】「認識=道具/媒体」説とその困難 自然な考え方(フオアシユテルング)によれば、哲学にあたっては、異なるそのものに、すなわち真に存在するものを現実に認識することへと進むに先立って、必要となる事柄がある。それはつまり、あらかじめ認識に関して理解しておくことである。その場合認識は道具であって、それを通じて絶対的なものが我がものとされるとみなされているか、あるいはそれを手段であり、これを介して絶対的なものが見てとられる運びとなる、と考えられているのである。
このような懸念を認識についてあらかじめ抱くのは正当なところであるように見える。それは一つには、感性、悟性、理性などさまざまな種類の認識が存在し、その内のあるものは他のものと比べて、この真に存在する絶対的なものの認識という究極的目的を到達しようとする際により適切なものであろうから、その限りではまた、その認識の種類の間で選択を誤ることがありうる以上、その選択について決定しておく必要があるからである。
さらにもう一つには、認識とは一定の種類のものであり、特定の範囲を伴った能力のことであるから、その本性と限界とをより詳細に規定しておかなければならない、ということである。そうしなければ、どちらの場合についても、真理の天界の代わりに、誤謬の雲海がつかまれることになるだろう。
こういった懸念は、おそらくは一箇の確信にさえ転じるに違いない。要するにしまいには、自体的(アン・ジッヒ)に存在するものを、認識を通じて意識が獲得しようとする企てのすべてが、その概念において矛盾しており、認識と絶対的なものとの間には、両者を端的に分断する境界があるとされてしまうのである。
◆
◎「ツァラトゥストラはこう言った」ニーチェ(1844~1900)。 有名な「神は死んだ」という言葉で表されたニヒリズムの確認から始め、あるがままの人間存在の意味を考えた。
【第1部】ツァラトゥストラの序説1 ツァラトゥストラは、30歳になったとき、その故郷を去り、故郷の湖を捨てて、山奥に入った。そこで自らの知恵を愛し、孤独を楽しんで10年ののちも倦むことを知らなかった。しかしついに彼の心の変わる時が来た。――ある朝、ツァラトゥストラはあかつきとともに起き、太陽を迎えて立ち、次のように太陽に語りかけた。
「偉大なる天体よ!もしあなたの光を浴びる者たちがいなかったら、あなたは果たして幸福といえるだろうか。この10年というもの、あなたは私の洞穴をさして登ってきてくれた。もし私と、私の鷲と蛇とがそこにいなかったら、あなたは自分の光にも、この道筋にも飽きてしまったことだろう。しかし、私たちがいて、毎朝あなたを待ち、あなたから溢れこぼれるものを受け取り、感謝して、あなたを祝福してきた。見てください。あまりにもたくさんの蜜を集めたミツバチのように、この私もまた自分の貯えた知恵を煩わしくなってきた。今は知恵を求めて差し伸べられる手が、私には必要となってきた。私は分配し、贈りたい。人間の中の賢者たちに再びその愚かさを、貧者達に再びおのれの富を悟らせて喜ばせたい。
そのために私は下へ降りて行かなければならない。あなたが、夕方、海の彼方に沈み、さらにその下の世界に光明をもたらすように。あまりにも豊かなる天体よ!私も、あなたのように没落しなければならない。私が今からそこへ降りて行こうとする人間たちが言う没落を、果さなければならぬ。では、私たちを祝福してください。どんな大きな幸福でも妬まずに見ることのできる静かな眼であるあなたよ!満ちあふれようとするこの盃を祝福してください。その水が金色に輝いてそこから流れ出し、いたるところにあなたの喜びの反映を運んでいくように!御覧なさい!この杯は再び空になろうとしている。ツァラトゥストラは再び人間になろうと欲している」
――こうしてツァラトゥストラの没落は始まった。
◆
*** 今週の教養 (西洋哲学の名著⑤)
◎「存在と無」サルトル(1905~1980)。 人間の意識のあり方=実存を精緻に分析し、存在と無の弁証法を問い極めたサルトルの主著。根源的な選択を見出す実存的精神分析、人間の絶対的自由の提唱などで世界に大きな影響を与えた(ちくま学芸文庫)。
【緒論】存在の探求 Ⅰ現象という観念 現代思想は、存在するものを、そのあらわす現われの連鎖に、還元することによって、著しい進歩を遂げた。それによって、哲学を悩ましているさまざまの二元論を克服し、これにかえるに現象の一元論をもってしようというのが、その狙いであった。果たしてそれは成功したであろうか?
まず存在するものにおいて内面と外面と対立させる二元論から、我々が解放されたことは確かである。もし我々が外面という言葉で、対象の真の本性をまなざしから隠すような表皮を意味するならば、存在するものの外面などは、もはや存在しない。また、その真の本性なるものも、もしそれが、当の対象の内面にあるがゆえに、予感し想定することはできても決して到達されることのないような、事物の秘められた実在であると解されるならば、そういうものはもはや存在しない。存在するものを表わすかかる現われは、内部でもなければ、外部でもない。それらの現われはすべて互いに等価である。それらの現われはすべて、他の諸々の現われを指し示すのであって、それらのうちのいずれも、特権を与えられてはいない。
例えば、力というようなものにしても、そのもろもろの効果(加速度、偏り、等々)の背後に隠されている形而上学的な、未知の種類の働きであるのではない。力はその諸効果の総体なのである。同様に電流も、隠れた裏面を持っているわけではない。電流はそれを表している物理・化学的な作用(電気分解、炭素線の白熱、電流計の指針の移動、等々)の総体より以外の何ものでもない。
これらの作用のいずれも、それだけは電流を顕示するのに十分ではない。しかしその作用は、それの背後にあるような何ものをも指示しはしない。その作用は、それ自身と、全体的な連鎖とを指示するのである。したがって、明らかに、存在と現象の二元論は、もはや哲学において市民権を得ることができないであろう。現われは、もろもろの現われの全連鎖を指し示すのであって、存在するものの全存在を独占するような隠れた実在を指し示すのではない。
