平野啓一郎の「小説の読み方」(2025年5月19~23日)
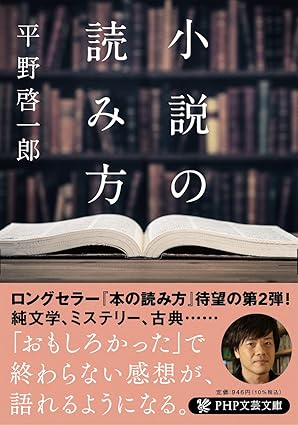
*** 今週の教養(小説の読み方①)
芥川賞作家の平野啓一郎さんが書いた「小説の読み方」(PHP文芸文庫、2022)を取り上げる。小説を単なる文学作品ととらえるのではなく、社会の一断面を切り取っている視点で考えてみたい。第1章「小説を読むための準備 基礎編」の冒頭を紹介する。関心のある方はぜひ読んで欲しい。
小説とは、何なのだろうか?小説という言葉の意味を知らない人はほとんどいないだろうが、その厳密な定義となると、意見はさまざまだ。そもそも、どうして小説のことを「小説」と呼ぶのだろうか。これは、字面からは必ずしも明瞭ではない。
「日本国語大辞典」(小学館)には、次の4つの語義が挙げられている。①中国の公認された、正式な文章で書かれた歴史である「正史」に対して、民間の取るに足らないような話を虚実を交えて散文体で記した「稗史」(はいし)から出た言葉。②①を踏まえ、novel、fable、fiction、romance、story、taleなどの訳語として蘭学時代から浸透し、後に、坪内逍遥によって、novelに限定されて用いられた言葉。③自説をへりくだって言う言葉。④他人の説や俗説を貶めて言う言葉。
③と④とは、取りあえず、除外しておこう。語源的な①は、現在でも小説というジャンルに期待されているところと、大体重なる印象だ。なにか、世間一般で正しいと信じられていること、常識だと思われていること、エライ人が、立派な言葉で「今という時代はこんな時代です」と抽象的に語ってしまったりすること――そういう諸々に対して、違和感を覚えたり、退屈したり、間違っていると考えたりして、もっと具体的で、生き生きとしていて、滑稽で、かなしくて、胸が躍るようで、切なくて、美しくもあり、また馬鹿馬鹿しくもある、感動的な話が人間にはあるはずだと信じること。しゃちほこばった言葉では、到底すくいとれないような現実が、人間にはあるのだと信じること。それが、小説が求められる理由だろう。
◆
*** 今週の教養(小説の読み方②)
文明開化を経て、ヨーロッパの「近代国家」を手本とした日本は、国家とは何ぞや、国民とは何ぞや、というしかつめらしい「正史」に対して、それらの国々が、普通の人が普通の言葉で書きつづる「稗史」(はいし)としてのnovelを持っていることに注目した。そこで採用されたのが、②で見るように「小説」という言葉であり、私たちは、特に以後の小説を、それ以前の散文体文学と区別して、「近代小説」と呼ぶのである。だから、小説というものは、いみじくも日本の代表的な近代小説家の1人、森鴎外が「何をどんな風に書いてもいい」と書いている通り、自由に、書きたいことを書くことにこそ、意味があるのである。
ところで、私は最近、こうした語誌的に正しい「小説」という言葉の理解に加えて、文字通りにこれを「小さく説く」ものというふうに考えている。ウェブ時代に突入して、私たちの生活には、世界中のありとあらゆる情報が溢れかえることになった。その量は膨大で、しかも、時間とともに流れ去ることもなく、データとして刻々と蓄えられ続けている。一方で、私たちの毎日はといえば、相も変わらず24時間しかなく、寿命は80年を超える程度だ。どうやったって、そのすべてを網羅することなどできない。
私たちは、仕方なく、どんな情報とも、どんな言葉とも、せわしなく、広く浅いつきあいをするようになって、ふと我に返ると、自分は果たして、本当に、以前よりも、世間や人間に対する理解が深くなっているのだろうかと、不安に感じるようになっている。そういう時代に、小説は、まさしく「小さく説く」のである。
この広大無辺で、複雑極まりない世の中を、そして、そこに生きる人間の心の奥底を、誰の手のひらにでも収まるほどのコンパクトなサイズに圧縮して、濃密な時間とともに体験させてくれる。それが、小説だ。ネット時代に突入して、小説は、もう歴史的な役目を終えてしまったのだろうか? とんでもない! むしろ今こそ、小説は、その意味を更新して、私たちに必要とされている表現形式なのだ。
◆
*** 今週の教養(小説の読み方③)
前著「本の読み方」(PHP文芸文庫)では、小説をはじめとする本を、もっと深く味わうために、「スロー・リーディング」(ゆっくり読むこと)という方法を紹介した。本書でも、その方針は変わらないが、ここでは、まずとっかかりとして、具体的な4つのアプローチについて考えてみよう。
鳥の鳴き声に見られる文法構造から、人間の言語の起源を探るというユニークな研究をしている岡ノ谷一夫さんは著書「小鳥の歌からヒトの言葉へ」(岩波書店)の中で、ノーベル医学生理学賞を受賞したニコラス・ティンバーゲンが、動物行動学の基本として挙げた「4つの質問」なるものを紹介している。その4つとは、動物の行動の①メカニズム②発達③機能④進化、に関するものだ。一見、ややこしい話のように感じられるかもしれないが、そうでもない。ざっと見てみよう。
「メカニズム」では、例えば、「小鳥が鳴いている」時に、その小鳥の脳神経系や内分泌系などが、どんな仕組みで働いて、その「鳴く」という行動が可能になっているのかを考えることがテーマとなる。「発達」では、卵からかえった鳥が、ヒナから成鳥になる過程で、どうやって歌を歌うことを学習し、どんな形でそれが表れてくるのかが研究されることになる。どちらも「歌を歌う」という行動が直接引き起こされる要因(至近要因と呼ばれる)を考える学問であり、ジャンルとして近いものだ。
それに対して「機能」では、「歌を歌う」という行動が、その鳥にとってどういう意味を持っている、「進化」は、その鳥が、そんなふうな「歌を歌う」ようになったのは、どういった淘汰の過程を経たからなのかを考えることとなる。ここで研究するのは、なぜ、その鳥は「歌を歌う」のかという「究極要因」だ。
さて、どうしてこんな話をしているかというと、このティンバーゲンの「4つの質問」は、実は小説を読むときのアプローチとしても有効だからだ。小説はもちろん、読んで何かを感じることが一番だ。しかし、笑いまくった、悲しかった、という感想以上のことを誰かと語り合うためには、考える手立てを知っていくことが重要だ。
◆
*** 今週の教養(小説の読み方④)
小説の「メカニズム」について考えるというのは、多分、一番マニアックな読み方だろう。書き手寄りの読み方、と言ってもいいかもしれない。小説とは、舞台設定、登場人物の人数、配置と出入り、プロットの展開、文体・・・などなどが複雑に絡み合って出来上がったものである。作者は、それらの要素を様々に駆使しながら、読者にある一つの世界を提供しようとする。どうしてこの小説は、こんなに面白いんだろう? どうしてこの小説は、こんなにわけがわかんないのだろう? 人や動物の行動を、体の中の機能を分析することによって、なるほどと理解できるように、小説も、動かしている仕組みについて考え、理解することで、これまでとは全く違った風に見えてくることだろう。
庭を駆け回る犬を見て、愛らしいと感じる。しかし、ロボット犬と違って、どうして生きている犬はあんなに精密な動きができるのかを知ると、これまでとはまた違った感動を覚える。「メカニズム」を知る面白さというのは、そういうことだ。
「発達」というのは、その作家の人生の中で、どういうタイミングでその作品が出てきたのかということを考えてみることである。初期のものか、晩年に書かれたものかによって、同じテーマを扱っていても、掘り下げ方や切り口は当然のことながら違ってくる。一作だけを読んでみてもピンとこなかった話が、前作、前々作を読むことによって、「なるほど、あのテーマが、こういう形で発展してきたのか」と、急に理解できることがある。その作家の変化の過程をたどることによって、作品の奥行きが見通せるようになるのだ。
デビューした頃は、作者本人でさえ曖昧にしか捉えきれていなかった世界が、作品を重ねるほどに明確になり、深みを増してゆく。あるいは、ある時までは熱心に取り組んでいたはずのテーマが、急に出てこなくなって、別のテーマに関心が移ったりする。文体も変わるし、世界観も変わる。それはなぜだろう? 作者の内的な変化のせいか、それとも社会の変化のせいか? 一人の作家に絞って、そのプロセスをたどっていくことで、一作だけを読んでみた時には見落としていた多くのことに気づかされるだろう。
◆
*** 今週の教養(小説の読み方⑤)
「進化」というのは、社会の歴史、文学の歴史の中で、その小説がどんな位置づけにあるかを考えてみることだ。どの小説も社会の影響を受け、その時代の雰囲気に影響され、さらには先行作品、同時代の他の作家の作品に影響されながら書かれている。漱石や鴎外の小説があって、芥川の小説が登場した。「発達」が作家個人の歴史だとすれば、「進化」は、そうした文学史的な視点によるアプローチだ。
「機能」というのは、ある小説が、作者と読者との間で持つ意味である。人間の優しさを伝えたいと作者が意図し、読者がそのように作品を受け止める。あるいは、自分を理解してもらいたいと思って小説を書き、読者がそれを読んで、少しだけ作者のことがわかったような気になる。現代社会の複雑さを映し出す。人間の心の暗黒面を追求する。いずれも、その小説が作者、読者双方に向けて持っている機能である。もちろん作者の意図と読者の意図がすれ違ってしまうことはいくらでもある。
この「機能」を単純化して示したのが、ジャンル分けである。小説はミステリーや恋愛小説、SF、ホラー小説など、さまざまなジャンルに分けられている。実際のところ、個々の作品は、それほどすっきりと分類されるわけでもなく、弊害が多いのがこのジャンル分けだが、にも関わらず、これがなくならないのは、読者がその作品の「機能」を知りたがっているからである。
小説を読み、ブログや課題などで感想を書く時に、この「4つの質問」すべてを網羅する必要はもちろんない。しかし、これらを知っておくと、とっかかりはずいぶんとスムーズになるし、他の人の感想を読んだ時に、どういう点に着目して議論しているのかがよくわかるようになるだろう。実際、文学賞の選考会では、はっきりとこの「4つの質問」が意識されるわけではないが、必然的にこうした観点に触れた議論がなされているのである。
