鶴見和子の内発的発展論(2025年7月7~11日)
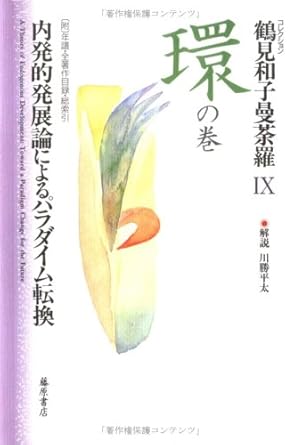
*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論①)
参議院選挙が始まった。「東京一極集中と地方をどうするか」は、「地方創生」のキーワードで語られる日本の永遠の争点だ。かつては公共事業を引っ張ってきたり、最近でも企業誘致が叫ばれたりする。外部の力を借りての発展だ。一方、地元の歴史や資源を見直す「内発的発展論」もあり、社会科学者・鶴見和子の理論が著名だ。近江加奈子氏(東洋大助教)の論文から要約して鶴見理論を紹介する。
【第1回:内発的発展論とは何か】 鶴見和子が1970年代に提唱した「内発的発展論」は、従来の外発的な近代化・開発モデルに対する根源的な問いかけである。この理論は、発展とは何か、誰のための成長かという根本的な問題意識から生まれた。欧米主導の開発理論が非西欧社会にとっていかに不均衡で画一的であったかを批判し、地域の文化、歴史、風土に根ざした「内側からの変化」にこそ真の発展の可能性があると説く。鶴見は、外部から押し付けられた制度や価値観ではなく、その土地に生きる人々の経験や知恵に着目した。特に柳田国男の民俗学に学び、常民の語りの中に社会変動の兆しを見出した点が特徴的である。
また、アニミズム的な自然観を重要視し、人間が自然と断絶することなく共にあるべき存在であるという視点を強調した。これは、戦後日本において急激に進んだ工業化や都市化の中で自然との断絶がもたらした弊害を批判するものであった。鶴見は、水俣病という深刻な環境公害に取り組む中で、自然とのつながりを失った人間社会がいかに脆弱であるかを痛感する。被害者が自らの体験を語り、地域社会が再生へ向かって歩み始める過程こそが、内発的発展の象徴であり、理論の出発点でもあった。
この理論のもう一つの特徴は、発展を単なる経済成長やインフラ整備ではなく、「価値の創出」と捉えた点である。人間の尊厳、文化の持続、地域のアイデンティティといった非物質的側面を中心に据えた視座は、当時としては非常に先進的だった。鶴見はまた、内発的発展がグローバルな問題解決にも通じる可能性があることを見抜いており、ローカルな実践が普遍的な意義を持ち得ることを理論的に提示した。これにより、内発的発展論は、単なる日本の地域理論にとどまらず、世界各地の発展戦略を再考する枠組みとして注目されるようになる。
このように、鶴見の内発的発展論は、外から与えられる開発に対するオルタナティブな道として、地域の内に宿る創造性や倫理、そして共生の思想を重視する理論体系である。人々が自らの文化と環境の中で主体的に変化を生み出し、持続可能な社会を築くという理念は、現代においても強い示唆を与えている。そのため、内発的発展論は今なお各分野で引用され、教育、環境、地方創生など多様な課題に応用されている。
◆
*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論②)
【第2回:西欧の内発的発展と鶴見理論の違い】 1970年代以降、欧米においても開発概念の見直しが進み、従来のGDP重視・工業化一辺倒の近代化論に代わる視点が模索された。その中で注目されたのが、スウェーデンのダグ・ハマーショルド財団によって発表された『もう一つの発展(Another Development)』報告書である。これは、地域に根差した人間中心の発展を提唱し、自然との共生、多様な価値の尊重、ジェンダー平等、文化の持続といった理念を盛り込んでいた。この報告書は、西欧内部から従来の開発援助やグローバル資本主義への疑問が表出した象徴であったが、その主な目的は政策提言であり、社会変動理論としての体系性には限界があった。
それに対して、鶴見和子の内発的発展論は、単なる援助の枠を超えた包括的な社会理論として構築されている。鶴見は西欧の学術研究に精通しつつも、アジア的世界観、特に東南アジア諸国の文化的実践や語りに着目した。彼女は、スリランカ、タイ、中国などでフィールド調査を行い、地域住民が自らの生活に基づいて編み出した知恵を重視した。このような「民衆知」は、西洋近代の理性や個人主義とは異なるものであり、共感、関係性、循環といった価値を内包するものだった。
また、鶴見理論は、柳田民俗学の継承と発展という側面も持つ。柳田が「常民」の生活に内在する知を掘り起こしたように、鶴見もまた常民の語りの中に発展の原点を見出した。西欧の理論がしばしば「普遍」を掲げるのに対し、鶴見は「多元」を基軸とした。それゆえ、彼女の理論は、近代化によって排除されがちな文化や価値観を擁護する傾向を持ち、多様な発展モデルの正当性を支える理論的基盤を提供する。
さらに重要なのは、鶴見が発展を「内面の成長」や「意味の再構成」と捉えていた点である。彼女は、経済的指標や技術水準の高さではなく、人々が自らの生活世界に意味を見出し、それを肯定的に再構築する力こそが、発展の本質であると説いた。これは、欧米での「ポスト開発論」や「脱成長論」とも親和性を持ち、今日の持続可能な社会を模索する理論的枠組みとも響き合う。
このように、鶴見の内発的発展論は、西欧で展開された「もう一つの発展」論とは異なる地平に立つ。それは、非西欧的価値を単なる代替案として消費するのではなく、理論の中心に据えて社会の在り方を根本から問い直すアプローチである。この点で、鶴見の理論は、グローバルな南北問題や地域格差、文化的均質化への批判として、今なお極めて有効である。
◆
*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論③)
【第3回:鶴見理論の4つの柱】 鶴見和子の内発的発展論は、単なる社会批評ではなく、明確な理論構造を持つ社会変動モデルとして提示されている。その中核には、4つの柱と呼ぶべき理論的視座が存在する。第1の柱は「価値多元論と規範性の両立」である。鶴見は文化相対主義の立場を取りつつも、人間の尊厳や自然との共生といった普遍的規範の存在を否定しない。このバランスは、多元的価値を単なる多様性として放置するのではなく、それらを照らし合わせ、より良き社会を構想する倫理的基盤を与える。
第2の柱は「常民の生活から社会変動を捉える視点」である。社会変化は上からの制度改革ではなく、日常生活に根ざした実践の中から静かに生まれてくる。鶴見は、民俗学的手法を用いて、地域住民の語りを丁寧に聞き取り、そこに内在する変革の契機を理論化した。特に注目されたのは、水俣病の患者たちが示した「語る力」である。彼らの苦しみの中にある希望や再生の兆しを、鶴見は社会理論として昇華させた。
第3の柱は「人間は自然の一部である」という自然観である。これは、近代社会が築いてきた自然支配の思想とは対極にある。水俣病がもたらした教訓の一つは、自然との断絶が人間社会に重大な病理をもたらすという点であり、鶴見はそこに警鐘を鳴らすと同時に、自然との新たな関係性の構築を提案した。自然を単なる資源として消費するのではなく、共に生きる存在として尊重することが、持続可能な社会の鍵となる。
第4の柱は「創造性としての内発性」である。鶴見は、定住者、漂泊者、一時漂泊者という3つの存在類型を提示し、彼らの出会いの中から新たな知と文化が生まれるとした。これは、単なる伝統の保守ではなく、新たな意味づけの営みとしての「創造的伝統」を重視する立場である。異質なものとの出会いによって自らの文化を再定義し、深化させる力こそが内発性の本質だという主張は、現代の多文化共生社会にも示唆を与える。
以上の4つの柱は、鶴見が構想した内発的発展論を静的な郷愁の理論から、動的かつ創造的な社会理論へと高める要素である。これらは単独で機能するものではなく、互いに補完し合いながら、複雑な現実社会に働きかける力を持っている。
◆
*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論④)
【第4回:理論の現代的再構成】 鶴見和子の内発的発展論が提唱された1970年代以降、日本社会を取り巻く環境は大きく変化した。高度経済成長期を経て、現在では少子高齢化、地域の過疎化、環境問題の深刻化といった新たな課題が浮上している。こうした現代の文脈において、内発的発展論の価値は改めて問い直されている。とりわけ注目されているのは、理論の「再構成」という視点である。鶴見が提示した定住者・漂泊者・一時漂泊者の三分類は、移動性と定住性の間に揺れ動く現代社会のリアリティに適応するために新たな読み替えが求められている。
たとえば、現代ではUターンやIターンと呼ばれる都市から地方への移住者、あるいは関係人口といった柔軟な地域関与の形が注目されている。こうした人々は、単に生活拠点を移すのではなく、地域に新たな価値や資源を持ち込み、定住者と漂泊者の橋渡し的存在として機能する。また、彼らの関与は、地域の伝統や文化を保守するだけでなく、再創造する契機ともなっている。このように、内発的発展とは単なる伝統の継承ではなく、今を生きる人々が主体的に伝統と向き合い、未来へ向けて意味づけを行うダイナミックなプロセスである。
さらに、発展途上国における内発性の実践も重要な論点である。多くの地域で「伝統」や「文化」は、植民地主義や国家による再編成を経て、政治的・経済的目的に利用されてきた歴史を持つ。そのため、内発性を単純に「地域固有のもの」と捉えることはできない。しかし、その中でも現地の人々の語りや実践を丁寧に掘り起こし、それを理論化する作業は、現代の社会科学において重要な意義を持つ。鶴見が行ったように、「語り」に耳を傾けること、それを通じて社会の再構築を目指すことは、今なお有効な方法論である。
また、グローバル化が進む現在においては、地域の内発性を守ることが同時にグローバルな問題への対抗軸ともなる。内発的発展論が提示する「人間と自然の共生」や「共感に基づく社会の再構成」は、気候変動や社会的分断といった現代のグローバル課題にも通じる思想である。今後は、内発的発展論をもとにした新たな実践と理論の再構築が求められており、そのためには異分野・異文化の対話と協働が不可欠である。
このように、内発的発展論の現代的再構成は、理論の深化だけでなく、新たな実践の可能性をも開く。地域と世界を結ぶ知のネットワークをいかに構築するかが、今後の課題となるであろう。
◆
*** 今週の教養講座(鶴見和子の内発的発展論⑤)
【第5回:内発的発展論の展望と可能性】 鶴見和子が提唱した内発的発展論は、今後の社会における持続可能な発展モデルのひとつとして、理論的・実践的価値が再評価されつつある。特に、地域創生、環境保全、教育、ジェンダー、文化多様性など、さまざまな分野において応用可能な理論であるという点において、その射程は広い。今回は内発的発展論の今後の展望と実際的な応用可能性について考察する。
まず注目されるのは、地域社会における具体的な実践事例である。たとえば、外部からの移住者が地域に新たな知見や技術を持ち込み、地元の人々と協働することで新しいコミュニティが形成されている事例が各地に見られる。これらは、鶴見の理論における「定住者」「漂泊者」「一時漂泊者」の協働モデルを現実に体現しているものであり、単なる移住政策や地域支援とは異なり、内発性に根ざした社会変革の兆しを示している。こうした動きは、地域文化の再発見と創造、地場産業の再構築、教育の革新など、さまざまな分野に波及している。
鶴見は「地域アーカイブ」の意義を強調していた。地域住民が自身の歴史や語りを記録し、蓄積・公開することは、単なる資料保存にとどまらず、次世代への知の継承、社会的アイデンティティの再確認、他地域との比較による新たな学びを生み出す装置となる。アーカイブは、知識の民主化と多様化を促進し、地域と世界をつなぐインターフェースとして機能する可能性を秘めている。
内発的発展論は、教育分野においても強い影響力を持ち得る。画一的な知識の伝達ではなく、子どもたちが自らの地域や文化に根ざした問いを持ち、それに基づいて学びを深める教育のあり方は、内発性を育む教育実践といえる。こうした教育観は、批判的思考力と創造性を育むと同時に、地域社会の担い手を育成する基盤となる。グローバルな視点から見ても、内発的発展論は持続可能な社会構築のための一つの道筋を示している。環境破壊、経済格差、文化の画一化といった課題に対して、ローカルな知と実践に基づくアプローチは、有効な代替案となり得る。内発性とは、単に自己完結することではなく、外部と対話しながら自らを再構築する柔軟な力である。
鶴見和子の内発的発展論は、今なお時代を超えて有効な理論であり、多くの分野に波及可能な柔軟性と包摂性を持っている。今後は、この理論をさらに深化させ、地域の現場で実践し、世界と共有していくことが求められる。学術、行政、地域住民、そして若い世代が協働し、知と実践の循環を生み出す環境づくりが必要不可欠である。
