ライフシフトの未来戦略(2025年18~22日)
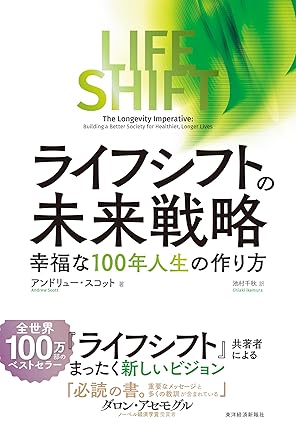
*** 今週の教養講座(ライフシフトの未来戦略①)
選挙で焦点になる多くの問題は、少子高齢化に行き着く。高齢化を暗いテーマと考えず、戦略を定めて積極的に適応すべきだと訴える「ライフシフトの未来戦略」(アンドリュー・スコット著、2025、東洋経済新報社)を取り上げる。著者は英国の経済学者。リンダ・グラットンとの共著で「人生100年時代の人生戦略」を提唱したことで知られる。ネット通販のサンプル版にある「はじめに」を紹介する。
★
あなたはもっと時間が欲しいだろうか。もし私が今日あなたの時間を1時間増やしてあげようと言ったら、どう思うだろう。実際には私があなたの時間を増やすことはできないけれども、ある秘密を教えてあげることはできる。誰もが知っているはずなのに、その知識に基づいて行動していないだけだ。あなたの持ち時間はすでに増えているのだ。平均寿命が延びているからだ。過去100年の間に世界の平均寿命は10年ごとに2、3年のペースで伸びてきた。
私が時間を増やしてあげようといった時、喜んだに違いない。では、寿命が延びることにより、自分の持ち時間が増えることを同じように歓迎するだろうか。新しい選択肢を手にできたと思うのか、それとも複雑な思いを抱くだろうか。長生きが本当に恩恵をもたらすのか、不安を感じるのか。多くのの人は後者の感情を抱いている。人々は今もっと時間が欲しいと思っている反面、寿命が延びることにより増える時間は、病気に苦しんだり、衰弱したり、お金の面で困窮したりする羽目になるのではないかと恐れているのだ。
しかし、老いの時代を健康に生き、活発に活動する日々を送れるとすれば、その恩恵は計り知れない。健康と生産性を保ち、社会と関わり続けられる期間が長くなるほど、高齢になった時の選択肢が広がり、長寿の恩恵を実感できる。将来もっと長く生きるようになると思えば、現在の行動も変わる。人生全体の生き方を考え直すようになるのだ。
◆
*** 今週の教養講座(ライフシフトの未来戦略②)
私たちは高齢になるまで生きる可能性が高くなっていることに十分適用できていない。問題はそれほど大きな変化だと感じづらいことだ。歴史上どの時代にもお年寄りはいたが、今起きつつある変化が本当に革命的な点は、若者や中年が、非常に高齢まで生きることが当たり前になったことにある。高齢者は少数派だったが、多数派になろうとしている。この新しい状況は、あらゆる物事を変える。より良い結果を手にするためには、未来への投資をもっと増やさなくてはならない。寿命が延びた結果、避けて通ることのできない必須課題が生まれたのである。
必須課題とは、よい老い方をすることだ。本書では長寿化がもたらす抜本的な変化と、それによって持ち上がる新しい課題をテーマにする。私たちは個人単位でも社会全体でも、「エバーグリーン」への転換を果たさなくてはならない。英語辞典によると、エバーグリーンとは「季節を通して緑の葉をつけ機能し続ける」常緑植物について用いられる言葉だが、広い意味では、常にあらゆる局面で新鮮さを失わない状態を表す。私たちは長い人生でこれを目指すべきだ。
人生が長くなるのにあわせて、健康やその他の重要な要素が機能する期間も長くしなくてはならない。老い方を変えることにより、人生で増えた時間を最大限有効に活用する方法を見出す必要がある。本書では、エバーグリーン型への転換を遂げるためにどのようなイノベーションが必要とされるのか述べたい。人生設計やキャリアプランの立て方、医療制度や経済と金融業界のあり方、高齢者であることや老いることについての文化や思想をどのように根本から変えるべきかを論じる。
長寿化は本来、非常に重要なテーマであるにもかかわらず、それに相応しい関心が払われているとは言えない。長寿化が話題にされる場合、しばしば誤った認識がまかり通っている。高齢者の数が増えることにしか目が向けられないことが多いが、このような無関心と誤解を是正したい。気づくべきは、高齢化社会ではなく長寿社会なのである。
◆
*** 今週の教養講座(ライフシフトの未来戦略③)
私はロンドンビジネススクールで世界経済の講座を担当している。最初の授業で学生たちに投げかける問いがある。「向こう数十年の間に、あなたたちの人生とキャリアに大きな影響を及ぼすトレンドはどのようなものだと思うか」という問いだ。真っ先に上がる2つの要素はいつも同じだ。人工知能(AI)と気候変動である。
この2つのテーマをひとしきり議論した後、学生たちはほかの要素にも目を向け始める。誰かが「人口動態の変化は」と発言すると、私はもう少し掘り下げた議論を促す。人口動態の変化とは何を意味するのかと尋ねると、決まって「社会が高齢化して高齢者の数が増えることだ」と学生たちは言う。学生たちの声は暗い。高齢化の影響は常にネガティブなものと考えられているようだ。
AIと気候変動に関しては議論が熱心に行われる。ところが高齢化社会に関しては、全く盛り上がらない。高齢者の数が多くなるというだけで話が終わってしまう。高齢者が増えることは悪材料であり、対処する手立てがないと決めつけているかのように見える。高齢化社会をめぐる議論は、際限なく膨れ上がる医療費、年金危機、認知症、介護施設の話題にとどまることがほとんどだ。変革や適用への意欲をかきたてられず、受忍と諦念が見て取れる。あくまで高齢者にかかわる問題であり、ビジネススクールで学ぶ学生たちの世代には関係ないと思われている。
本書では長寿化がAIやサステナビリティと同じくらい私たちの未来にとって重要なテーマであることを示したい。未来の暗い結果を避けるためには抜本的な変化が不可欠である事を知ってもらいたい。長寿化は私たちの人生を根本から変える。若い世代が長寿に備えるのを支援するより、高齢者のニーズに応えるために支援が費やされることになれば、世代間対立が激化するだろう。今求められているのは、人類を取り巻く状況の劇的な変化に適用することだ。長寿化で突きつけられている課題を克服し、エバーグリーン型への転換を遂げる必要がある。
◆
*** 今週の教養講座(ライフシフトの未来戦略④)
第1部では、エバーグリーン型への移行に関する課題をひと通り説明し、以下の問いを検討する。平均寿命にどのような変化が起きたのか、今後どのような変化が起きる可能性が高いのか、長時間に伴って対処する必要がある課題はどのようなものか、私たちはどのように老いていくのか。エバーグリーンの課題がなぜ重要なのか、なぜそれが人類にとって新しい時代の到来を意味するのか。
第2部では、エバーグリーンの課題を達成するため、どのような大掛かりな変化が必要とされるかを論じる。具体的には以下の議論を進める。医療制度と個人の行動をどのように変える必要があるのか。長くなった人生で必要とされるお金をどのように賄い、長時間の経済的な恩恵をどのようにして引き出せばいいのか。私たちの職業人生はどのように変わるのか。お金が足りなくなるリスクを取り除くために金融業界はどのように変わるべきか。私たちはお金に関わる行動をどのように変えるべきか。
第3部では、老いることについての考え方と文化と心理をどのように変える必要があるかに目を向ける。どのように生きがいを生み出せばいいのか。老いに対する心理と文化をどのように修正し、どうやって年齢差別的な固定観念を消す捨て去るべきなのか。世代間の公平をどのように確保すればいいのか。エバーグリーン型の社会を築く上で、大きな障害は何か。障害を乗り越えるにはどうすればいいのか。
世界各国の政府と政策決定者たちは、何十年も前から大規模な人口動態上の変化が進んでいることを認識していた。しかし高齢化にばかりに関心が払われる結果、真に切実な課題に十分に目が向いていない。問題は、高齢者の数が増えることにどうやって対処するかではない。長い人生に対処するため、私たちが今、どう行動するかが問題なのだ。これまで対策らしい対策が取られてこなかったことを考えると、いますぐに大きな変化を起こす必要がある。さあ、エバーグリーンの課題に向き合おう。
◆
*** 今週の教養講座(ライフシフトの未来戦略⑤)
リンダ・グラットン(Lynda Gratton)とアンドリュー・スコット(Andrew Scott)が提唱した「ライフシフト(The 100-Year Life)」は、平均寿命100年時代を前提に、私たちの人生設計や働き方、生き方を根本的に見直すべきだという問題提起です。これは単なる長寿の話ではありません。「人生が長くなった」という事実が、教育、仕事、家族、引退、資産形成、健康、そしてアイデンティティの形成にまで、複合的な影響を及ぼすという構造的な議論です。
従来の人生モデルは、「教育→仕事→引退」という3ステージ型でした。しかしこのモデルは、寿命が70~80年だった時代の設計であり、100年時代にはもはや機能しません。ライフシフトでは、新しい人生モデルとして「マルチステージ型」の人生を提唱しています。このモデルでは、人生が複数のフェーズに分かれ、学び、働き、休み、転職し、再び学ぶというように、柔軟にステージを移動していくのが特徴です。
例えば、30代で一度仕事を離れ新しいスキルを学ぶ「トランジション期間」を設ける、50代で起業する、60代で異業種に転職する――そんなキャリアの多様性が現実的になると同時に、必要となるのが「変身資産(Transformational Assets)」と呼ばれる能力です。これは、変化に適応する力、人間関係の構築力、自分を再定義する力など、長い人生を柔軟に生き抜くために不可欠な資産です。
また、ライフシフトでは「無形資産」の重要性が強調されます。たとえば健康、人間関係、学び直しの習慣、好奇心、自律性などです。これらは給与や年金とは異なり、数値化できないが人生の質を左右する決定的要素です。100年を生き抜くには、金融資産以上に無形資産の戦略的蓄積が必要だと説いています。
ライフシフトは、高齢化社会における新しい人生設計の羅針盤です。年齢に縛られず、個人が自らの人生をデザインし直す時代。教育の再設計、企業の雇用制度の見直し、社会保障の抜本的改革が求められる今、ライフシフトの思想は、個人と社会の両面から大きな示唆を与えています。
