池澤夏樹の「本の読み方」(2025年8月25~29日)
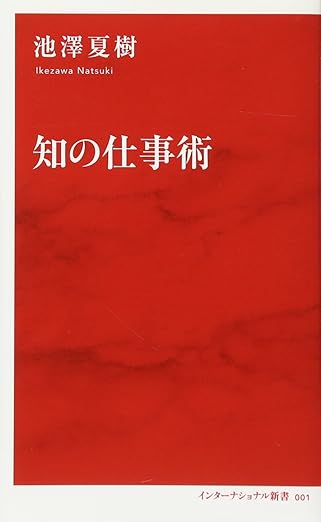
*** 今週の教養講座(池澤夏樹の本の読み方①)
今週は作家・池澤夏樹氏の「本の読み方」を紹介する。時間に限りがある中で、本をどう読むかは悩ましい。世界と日本の文学全集(河出書房新社)を編集した作家の極意に触れる。「知の仕事術」(集英社インターナショナル、2017)から抜粋する。
◎速読と精読を使い分ける 本をどのくらいの密度で読むかは、本によって違ってくる。小説などフィクションの場合、最初の50頁はできるだけ丁寧に読んで文体をつかむとよい。フィクションは「プロット(筋)と文体」からなる。ミステリーなどはプロットにひかれて先へ先へと読み進めるように作ってある。それに対して濃厚なこった文体のいわゆる「純文学」の作品であれば、文体を楽しみながら読むことになる。誰もジェイムズ・ジョイスの長編「ユリシーズ」を3日で読もうとは思わないだろう。この小説はチャプターごとに文体が異なり、それが大きな読みどころとなっている。
フィクションを読む時、登場人物の名前が覚えにくい場合は、メモを取りたい。人と人の関係がわかったら、その関係も書いておく。登場人物一覧がついている本もあるが、自分で一度メモを取る方がしっかり覚えられる。その話の世界に没入できるようになる。
どのくらいの密度で読むかも本ごとに違ってくる。最初は素早くざっと最後まで読んでから、面白いと思った箇所に戻ってそこだけを味わって読むというやり方もある。言ってみれば、速読と精読を使い分けるわけだ。使い分けは、自分と本の相性で決まる。気に入った本なら、生涯2度、3度と読むこともある。毎年1回読み直す本があってもいい。
読書とはその本の内容を自分の頭に移して行く営みだ。きちんと読んだ本は、自分がものを考える時、必ず役に立つ。あの本の作者が言っていたことが今ここで応用できるなという場面が増え、言ってみれば、世間との対立の場で力強い武器になる。役に立つ本が増えるほど、物の見方が複眼的になり、うまくものが考えられるようになっていく。これはディベートで相手を負かすためでも、物知りぶって威張るためでもなく、自分なりの世界図を自分の中に構築するために必要なことだ。
◆
*** 今週の教養講座(池澤夏樹の本の読み方②)
◎フィクションとノンフィクション 小説などのフィクションならば、目次はそれほどていねいに読まなくてもいい。フィクションの目次は、チャプター(章)の名前が並んでいるだけで、あまり意味がない。雰囲気がわかるだけで十分だ。登場人物一覧表や地図がついていることもあるが、読み始める前にそんなに見なくていい。読んでいる途中に戻って参照するためのものだ。
フィクションでない本の場合、目次はていねいに見るべきだ。ノンフィクションの目次は本の内容全体を表しているから、目次を読めば本の構成が大体わかる。思想書や研究書の場合、読み出す前に展開を頭に入れておくかどうかで、理解度が変わってくる。本によっては、本文の後に解説やあとがきがついている。先に読んだ方がいい場合もある。本文に取りつくのが大変な、読み手に取って難解な本を読む時に当てはまる。
文庫本の解説は、ほとんど日本特有のものだ。これは事前に読んで損をしないことが多い。もっともとんでもない見当違いのものも多く、それを分析したのが斎藤美奈子の「文庫解説を読む」という本だ。ツッコミが鋭くて、読んでいて笑ってしまう。
文庫の解説も、フィクションの場合は微妙で、注意が必要だ。いわゆるネタバレまでいかなくても、内容に踏み込みすぎた解説を先に読むと、新鮮味がなくなる。フィクションの場合、親切な解説者なら内容に立ち入る際は「ここから先は」などと警告を発した上で、話を先に進める。ともあれ、ほとんどの解説は役に立つ。手ごわそうと思う本を手に取る場合、解説で少し噛み砕いてもらってから本文に取りつくと、少し楽になる。
訳書の場合、翻訳者が解説を書いていることが多い。たいていの翻訳者は信用できる。原書の内容を理解した人の解説であるはずだから、読む際の手引きになる。著者や出版社の側から言えば、文庫本の解説は影響力のある宣伝の一つだ。上手に褒めてくれる人に頼まなければならない。
◆
*** 今週の教養講座(池澤夏樹の本の読み方③)
◎古典とのつき合い 古典を読んだかと言われると、詰問されているような気分になる。会食の場で古典が話題になったとしよう。読んだ人たちは得意そうに論じているから、読んでいない自分は話についていけなくて肩身が狭い思いをする。古典は重機の運転免許のように特別な資格のようだ。
正直な話、古典はとっつきにくい。その人たちの日々の生活やものの考え方まで、全てが遠いものに思われる。ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」に出てくるアレクセイ・フョードルビッチ・カラマーゾフなんて長すぎるし、普段はアリョーシャで済ませているというのだから複雑だ。そういうことを知っていないと、先に進めない。地主と農奴、お金の単位がルーヴル、黒パンとかロシア正教の祭礼とか、社会のありようも今の日本と違いすぎる。それは「イーリアス」でも「史記」でも「古事記」でも「ハムレット」でも「白鯨」でも同じ。正当な文学全集に入っているもの、すべて読みやすくはない。
はっきり言ってしまうと、古典を読むのは知的労力の投資だ。最初はずっと持ち出し。苦労ばかりで楽しみは遠い。しかし大抵の場合、この投資は実を結ぶ。たくさんの人が試みて、うまくいったと保証されたものが、古典と呼ばれる。あなたの趣味がほかの人たちと全然違うのでなければ、最初の苦労を承知で手に取ってみるのは悪いことではない。ただし、結果が出るのはすぐとは限らない。つまらなくてダメだと思って放棄するのも読書の自由。何年も経って、時には何十年も経って、ふっと読みかけのものを思い出して再度挑戦すると、今度はものすごく面白いということもある。若い時に少しでもかじっておくと、後になって滋味がわかるようになる。
年齢とともに読む力も伸びるということだ。世間知が増すにつれて、あるいは人生の苦労を重ねた分だけ、本の内容の理解も深まる。そういうときになると、若い間にかじったことがちゃんと思い出され、ひょっとしたら今ならわかるかもしれないと改めてページを開くとものすごく面白い。そんな体験にが何度もあった。告白すればまだ、「ドンキホーテ」や「神曲」や「マハーバーラタ」や「太平記」を読んでいない。自慢ではないが、読んでいない古典は山ほどある。老いての楽しみに事欠くことはまずないだろう。
◆
*** 今週の教養講座(池澤夏樹の本の読み方④)
◎本を最後まで読むべきか 大人は子どもに対して「本は途中で投げ出さないで最後まで読みなさい」などと言いがちだが、そうではない。確かに読書習慣を身につけるために最後まで読むべきかもしれない。だが、それ以前に本と人のあいだには相性というものがある。つまらないと思ったら、それは子どもなりの一つの批評だから、尊重すべきだ。人には発達段階があり、その子にとってその本を今読むべき段階であるかどうかは親でもわからない。歯が立たないのであれば、つまらないのであれば、読むのをやめたいと思ったら、いったん投げ出していい。名著と思われている本であろうと、我慢して読む必要はない。
読む本の数が増えてきた大人が途中で投げ出した場合、それはつまらなかったということだから、放り出した本はその人の人生から消えてしまう可能性が高い。しかし子どもの場合、案外またあとで読むものだ。最初に読んだところまで内容を覚えているから、途中から読み進められる。子どもの頭はそれくらい柔軟だ。「星の王子さま」も子どもが初めて読んだときに面白いと思うとは限らない。「風の又三郎」だって「銀河鉄道の夜」だってそうだ。一度手に取った本を最後まで読むかどうかは、その本が自分に向いているかどうかを考えた上で決めればよい。面白くない本を最後まで読むよう強制され、本嫌いになるくらいなら、投げ出した方がよほどマシだと思う。
大人であっても相性はある。本屋でじっとにらんで、「これはいい本だ」と買った本であっても、残念ながら家で開いたらつまらなかったということは少なくない。本にも当たり外れがあるから、仕方がない。もちろんしばらく時をへて手にとり、面白いじゃないかと思いなおすことはあるだろう。ちょっとのぞいて合わないと思えば、ほかに行く。そういうわがままな読み方でも大事な本にいつかは行き着く。広く浅く読む方が、たくさんの本に会えるし、浅くと思っても、相性によっては深く引き込まれ、それが一生のつき合いになることもある。読書にカリキュラムはないし、卒業もない。永遠の留年状態である。
◆
*** 今週の教養講座(池澤夏樹の本の読み方⑤)
◎いわゆる名著を読むべきか かつてイギリスの雑誌が「あなたが実はまだ読んでいない必読書」と題したユニークなアンケート調査を行ったことがある。著名な研究者、学者評論家らはしぶしぶ白状するわけだが、「実は『ドンキホーテ』がまだ」とか「『ヘロドトス』は読んだけど『トゥキディデス』はまだ読んでいない」とか答えた。この特集が成り立ったのは、ひとかどの人物は名著を読んでいるという共通認識がある。
古典は長い時間をかけてみんなが読んできた書物だから、価値が保証されている。しかし、それがあなたに向いているかどうかは、また別の話だ。読んでいない必読書があったとしても、それは仕方ないというのが僕の考えだ。ただし、長い間いろいろなものを読んでいると、またこの本が出てきたな、自分はあの辺が抜けているんだろうなと気づくことがある。そういうタイミングで古典を手に取るのは、いいことだ。世界が広がるという意味で、読書のもたらす恩恵のひとつだろう。
例えば「薔薇の名前」(ウンベルト・エーコ著)を読んでいると、アリストテレスをのぞくぐらいはしたくなる。たとえ読み切れなかったとしても、関連箇所くらいは読みたくなる。そういう形で教養は広がっていくものである。
伝記について述べてみたい。イギリス人は非常に伝記が好きだ。書店に行くと「F」(フィクション)と並んで、バイオグラフィーの「B」という分類の棚がある。文学者に限らず有名人が亡くなると、ほどなく誰が伝記を書くかという話が持ち上がる。決まれば、基本的に家族も友人も協力を惜しまない。書簡を提供したり、長時間のインタビューに応じたりする。著者は何十人とインタビューをした上で、対象にべったり寄るのではなく、批評的な視点も持ち合わせた伝記をまとめる。こうした文化は日本にはないと思う。
エーヴ・キュリーの「キュリー夫人」は、いい伝記だった。先験的な理論を打ち立てた天才数学者エヴァリスト・ガロアについて書いた「ガロアの生涯――神々の愛でし人」(レオポルト・インフェルト著)という伝記がある。ガロアは1832年、ある女をめぐって決闘をすることになり、そこで負ったケガが原因で亡くなる。21歳という若さであった。ガロアは決闘前夜、「僕にはもう時間がない」と自らの数学理論を必死に書き残したという。それは他の数学者が理解するのに数十年かかったということをこの伝記で知った。
