宮本常一著「忘れられた日本人」(2024年9月9~13日)

*** 今週の教養 (忘れられた日本人①)
今週は民俗学者・宮本常一(1907~1981)の著書「忘れられた日本人」(1960、未來社)を取り上げる。人々の営みに分け入り、「素顔の歴史」と評された同書について、NHK・Eテレ「100分de名著」のテキスト(畑中章宏著)から紹介する。
◎概説 宮本常一は1907年、瀬戸内海に浮かぶ周防大島(山口県)の農家に生まれた。15歳の時に大阪へ出て郵便局員になり、大阪や奈良で小中学校の教員を歴任。民俗学を志し、柳田国男や渋沢敬三の知遇を得た。民俗学者はよく歩く。民間伝承や民間信仰、祭りなどの風物から日本人の「心」を探ろうとした柳田国男や折口信夫と、宮本の歩き方は異なる。柳田らのように目に見えない「心」ではなく、宮本は目に見える「もの」を入り口にした。生産活動などに用いられてきた「民具」を調べることで、私たちの生活史をたどることができると考えた。
民俗学は柳田国男が主流で、宮本は傍流とされ、「歩く・見る・聞く民俗学」と言われた。傍流の民俗学の重要性に改めて私が気づいたのは、2011年の東日本大震災だった。福島第一原子力発電所の事故という未曾有の災害を引き起こし、知識人たちは人類史や文明史といった「大きな歴史」の中でこの事態をとらえようとした。そうした論評は今も絶えることがない。しかし、こういうときこそ「小さな歴史」が重要なのではないかと思う。小さな集落の多様性や、個々の人生の機微を見つめ、普通の人々が各地でどのような生活を営み、過去にどのような人生を送ってきたかを考えなければいけないのではないか。震災は広範囲にわたり、被災地域ごとにその要素も異なるし、被害と向き合う人々の感情もひとくくりにはできないような事態だと考えた。
宮本は日本列島の隅々まで歩き、地域と民衆の個別性、多様性をつぶさに探った。その成果を堅苦しい報告書や論文ではなく、難しい用語を使わない親しみやすい形式で書いた。「忘れられた日本人」は、時に私たちの常識を覆すような「生活誌」の宝庫である。そこには閉じた「共同体の民俗学」から、開かれた「公共性の民俗学」へという宮本の意志と思想が潜在している。
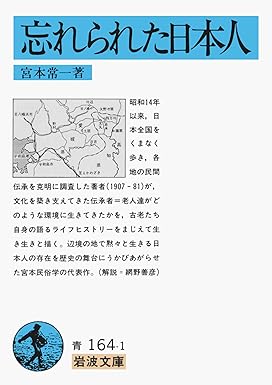
*** 今週の教養 (忘れられた日本人②)
◎民衆の民俗学 「忘れられた日本人」は13編からなっている。刊行時、宮本は52歳。実業家で民俗学に関心の深かった渋沢敬三が創設した研究所に所属していた。「忘れられた日本人」というタイトルには、日本人が高度経済成長という進歩と発展のとば口にさしかかり、近い過去にあった貧しさや苦労を忘れていないか。かつて歴史に存在した遍歴者や漂泊民、相互扶助の精神を持った人々のありようを忘れてはいけないと主張している気がする。
民俗学の目的は「経世済民」、世をおさめ、民を救うことだった。柳田国男は「遠野物語」で魂や死にまつわる怪異な伝承と人々がどう付き合ってきたかを描いている。潜在的な心を掘り下げて経世済民に至ろうとする道だった。折口信夫という天才肌の人物は、古代の神話や文芸に造詣が深く、新しい概念を作り出していった。渋沢は異なる方向を打ち出し、精力的に活動したのが宮本だった。民俗技術や民具の研究を進めながら経世済民を目指していくことになった。
柳田の遠野物語は「昔あるところに貧しき百姓あり。妻はなくて美しき娘あり。また一匹の馬を養う」という文だ。宮本の「忘れられた日本人」で最も有名な「土佐源氏」は「人をだましてもうけるものじゃから、うそをつくことは全てばくろうロというて、世間は信用もせんし、小馬鹿にしていった」とある。遠野物語は民間信仰が美しく幻想的に書かれ、方言を文語体にしている。宮本は馬喰のリアリティに富む語りをそのまま描いている。日常のやり取りや生業の異なる人間に対する尊敬がある。柳田民俗学が「心の民俗学」「霊魂の民俗学」となり、内面の研究にシフトする一方、渋沢や宮本は、生業や道具などを調査することによって過去の生活を見出そうとした。
宮本は渋沢から授けられた「大切なことは主流にならぬ事だ。傍流でよく状況を見て行くことだ」とう助言を守った。傍流は「オルタナティブ」と言い換えることができる。宮本は歴史を作ってきた主体として民衆や庶民を常に念頭に置いた。民衆は「愚昧の民」とされたが、宮本は名前を残さずに消えていった人々存在を含めて歴史を描き出そうとし、日本や日本人が一つではない事を示した。聞き書きにはよい老人に会うことが大切だと考えた。祖先から受け継いだ知識を「公」のもの考え、私見を加えないからだ。よい話者は青壮年時代に各地を歩き回った「世間師」と言われる人々に多く、自他の生活の比較があり、知識も豊富と考えた。
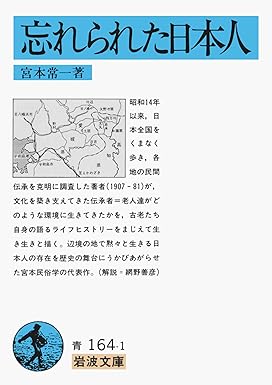
*** 今週の教養 (忘れられた日本人③)
◎したたかな世間の考察 本の冒頭に「対馬にて」と「村の寄りあい」の2編があり、伝統社会の合議の一例として「寄合」を取り上げている。宮本が対馬を訪れた時、古文書があることを聞き、見せてくれないかと頼んだ。区の承諾を得ないとダメだとなり、何日も時間をかけて複数の議題を同時並行しながら、みんなが納得するまで話し合って結論を出した。寄合は効率が悪くとも「熟議」と呼べるのではないでだろうか。寄合では言いたいことを言い合うが、宮本は「これは理屈ではない」と言う。過去の事例も遡上に載せ、経験や記憶をその場で持ち寄りながら話し合うことが重要であると。さらに「少なくとも京都、大阪から西の村々には寄り合いが古くから行われてきた。会合では郷士も百姓も区別はなかったようである。領主・藩士・百姓という系列の中では百姓の身分は低いものになるが、村落共同体の一員になると互角であったようである」とも書いている。
村には「年齢階梯制」もあった。同じ年齢層による横の結びつきで、若衆組、娘仲間、隠居組などがある。「講」のように信仰をともにする宗教的な集まりから発達したグループもあった。福井県敦賀の西の海岸沿いで聞いた「観音講」もそうだ。「『つまり嫁の悪口を言う講よの』と一人が言った。別の一人が、年寄りは愚痴の多いもので、つい嫁の悪口が言いたくなる。そこでこうしたところで話し合うのだが、そうすれば面と向かって嫁に辛く当たらなくても済むという」と書いてある。共同体では横のつながりも重要だった。話し合いの場では、共同体外の「世間」を旅してきた人の経験や情報が重視された。
女性ならではの世間もあった。「女の世間」の編によると、周防大島にはかつて、村の若い女性がある年代に達すると家を出て奉公などで現金収入を得て帰って来る秘密の習わしがあった。ある日突然出て行くが、父親は知らなくても母親は事情を知っていた。母親自身も娘の自分に同じことをしたからだ。嫁入り前に稼いだお金で京都や大阪をめぐることが、女性が教養を得るための社会教育で、明治以降はそれが慣習化していた。現在はひとりの人間が同時に複数の世間を持つことが必要とされているが、民族的な風習の中に今に生きる知恵がある。
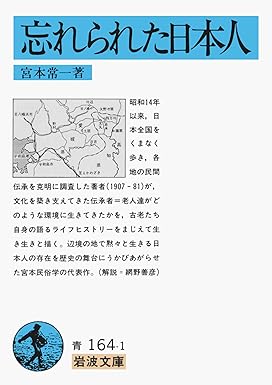
*** 今週の教養 (忘れられた日本人④)
◎「土佐源氏」の衝撃 「忘れられた日本人」では、文字を知らない庶民や何ら業績のない物乞いなど、歴史の片隅に追いやられた人たちが鮮やかに描かれる。進歩や発展の名のもとに斬り捨てられてきたもう一つの日本人の姿に迫っている。その代表的な人物に高知県山間部にある土佐梼原の橋の下に住む、目が見えなくなった物乞いの老人がいる。最もよく知られた「土佐源氏」で、宮本の代表作として大変有名になった。馬喰という移動をしながら牛馬を扱う仕事を生業とした人の生活誌だ。夜這いで生を受けたというこの男は、父親がわからず、母親も早くに亡くし、祖父母の手で育てられた。成長して馬喰となり、さまざまな女性と関係を結んできたが、今では物乞いになったという。
「あんたはどこかな?長州か。長州人は昔からよう稼いだもんじゃ。この辺りは木挽や大工で働きに来て」「私の話を聞きたいといいなさっても、わたしは何も知らんのじゃ。牛や馬のことなら知っとる。しかしほかのことは何も知らん」。老人が自慢できるのは、馬喰の仕事で牛を追いながら行く先々の村で出会った後家たちや裕福な家柄の人の妻との性遍歴の顛末だけだった。馬喰という移動者の生活や感情が見事に活写されている。実はこの話には創作が盛り込まれていると指摘されている。この人物が実在したのかどうかの検証によると、モデルは確かにいるが、土佐源氏はイコールではない。目が見えず、馬喰をしていたけれど、橋のたもとに立つきちんとした家に住んでいたことが判明している。宮本が各地で会った複数の聞き書きを混ぜ合わせて作った象徴的なキャラクターではないのかと思われる。
遠野物語にある「河童を見た」が事実かどうかという話につながっていく。「苦海浄土」の作者・石牟礼道子は、宮本の文章を読み返しながら遠野物語を思い浮かべたと書いている。「優れた民俗学者は文学者も兼ね、詩的インスピレーションを併せ持っているものだとつくづく感服される」と述べている。苦海浄土も事実そのままではなく、霊感と想像力で脚色し虚構化されることで強度を増した語りの部分があることは知られている。
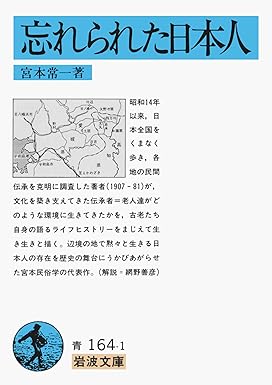
*** 今週の教養 (忘れられた日本人⑤)
◎「世間師」の思想 宮本常一の民俗学を特徴づける重要な言葉に「世間」がある。歴史学者の阿部謹也によると、古来日本にあったのは「世間」であり、「社会」は明治以降に輸入された概念だ。日本の「世間」は、西欧の個人を前提とした「社会」ではない。世間は一枚岩ではなく、いくつもの世間が折り重なっている。1人の人間は複数の世間に属しており、世間ごとに違った自分の複数の属性を使い分けている。多様性があるのだ。
親子や支配・被支配の縦の関係は、家父長的な同族結合の強い東日本の村に多いのに対して、西日本は「非血縁結合」、つまり「地縁結合」が強く、中間的な村もあると宮本はみている。歴史学者の網野善彦も岩波文庫版の「忘れられた日本人」の解説で、そこに注目する。「戦後、寄生地主制や家父長制が封建的として批判されたことが農村のイメージを一色に塗りつぶす傾向にあったのに対して、西日本に生まれた宮本氏は強く批判的であり、それを東日本の特徴と見ていた」と述べている。
宮本は「世間」という言葉を肯定的、積極的に用いた。日本の村落共同体は固定的で閉鎖的なイメージを持たれがちだ。稲作中心で、家や土地に縛り付けられた定住民の印象が強いからだろう。しかし漁民を見れば、漁をして移動し、立ち寄る先々の港に文化を伝えたりしながら、他の土地へも移動し、戻ってきた。日本の庶民は漁民でも農民でも自分たちが豊かになるために開拓民として新たな土地を切り開き、故郷から移動した。それが宮本の根本的な考え方だった。
宮本が記録した世間師は、放浪の旅をして帰ってくる存在である。共同体の外側にある文化や産業、生活を見て歩き、その価値を自らの共同体に持ち帰る。共同体の漸進的な発展はそんな風にもたらされた。忘れられた日本人収録の13篇のうち後半の6編は、6人の老人たちのライフヒストリーが並んでいる。中心にあるのが世間師という言葉だ。近代化によって政府や教育でもたらされる「上からの制度化された変化」ではなく、庶民が努力して知識や経験を獲得し、よりよい共同体を探ろうとした。そこに地道な変化に寄与してきた世間師たちがいた。必ずしも成功した例ばかりではない。宮本が言いたかったことだと思う。そしてまた、宮本自身も日本各地を歩く世間師でもあった。
